01 借り上げ社宅制度ってどんな制度?
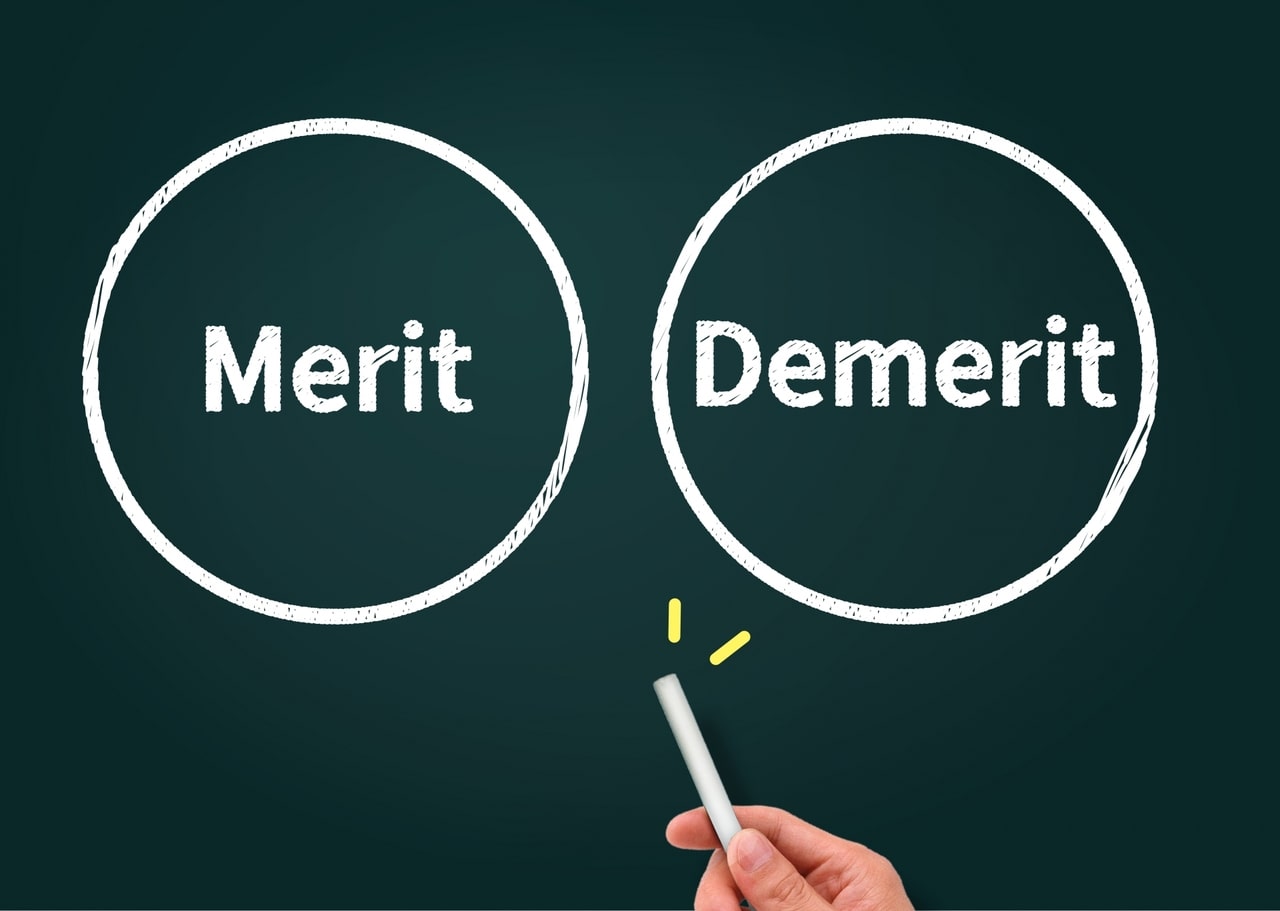
借り上げ社宅制度は、企業が社員の住居確保をサポートする福利厚生の一つです。従来の社有社宅とは異なる新しい形の住宅支援制度として、多くの企業で導入が進んでいます。ここでは制度の基本的な仕組みと特徴について詳しく見ていきましょう。
企業が用意する「社宅」の新しい形
借り上げ社宅制度とは、企業が民間の賃貸物件を借り上げて、社員に提供する住宅支援制度のことです。会社が不動産会社と賃貸契約を結び、その物件を社員に転貸する形で運営されます。
たとえば、新入社員のAさんが希望するエリアのマンションを、会社が大家さんと契約を結んで借り上げ、Aさんはその物件に住むという仕組みです。契約上の借主は会社となるため、社員は家賃の一部負担だけで質の良い住居を確保できます。
社有社宅との違いとは?
従来の社有社宅は、企業が土地や建物を所有・管理する形でしたが、借り上げ社宅では企業は物件を所有せず、賃貸として借り上げる点が大きく異なります。
この違いにより、借り上げ社宅では社員のライフスタイルに合わせた物件選びが可能になり、企業側も管理コストを抑えられるメリットがあります。
賃貸住宅を会社が借りることで実現する福利厚生
借り上げ社宅制度の核心は、会社が賃貸住宅の契約者となることで、社員の住居費負担を軽減する点です。通常、個人で賃貸契約を結ぶ場合、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用に加え、毎月の家賃を全額負担する必要があります。
しかし借り上げ社宅では、これらの費用を会社が負担し、社員は月額数万円程度の自己負担で住居を確保できます。社員負担は2〜3万円程度というケースもありますが、企業によって異なり、家賃の30〜50%程度を自己負担とする例も見られます
株式会社三央のような従業員の働きやすさを重視する企業では、こうした住宅支援制度を通じて社員の生活基盤をしっかりとサポートしています。
02 借り上げ社宅制度があると何がうれしい?

借り上げ社宅制度が整備された企業では、経済面だけでなく生活の質向上にも大きなメリットをもたらします。ここでは具体的にどのような利点があるのか、詳しく見ていきましょう。
家賃負担を抑えられる経済的メリット
借り上げ社宅制度の最大の魅力は、なんといっても大幅な家賃負担軽減です。一般的に収入の30%程度とされる住居費を、大幅に削減できることで可処分所得が増加します。
たとえば、月収30万円のBさんが家賃8万円のアパートに住んでいた場合、借り上げ社宅制度により自己負担が2万円になれば、月6万円、年間72万円もの節約が実現できます。この余裕資金は、スキルアップのための投資や将来への貯蓄、趣味や旅行などの充実した生活に活用できます。
希望に近い間取りやエリアが選べる自由度
社有社宅と比較して、借り上げ社宅制度では物件選択の自由度が高いことも大きなメリットです。会社が指定するエリア内であれば、間取りや設備、最寄り駅までの距離など、自分のライフスタイルに合わせた物件を選択できます。
具体的には、通勤時間を重視する方は駅近物件を、プライベート空間を大切にしたい方は広めの間取りを選ぶといった具合に、個人のニーズに応じたカスタマイズが可能です。
住宅手当との違いと比較
住宅手当と借り上げ社宅制度では、税制上の扱いが大きく異なります。
項目住宅手当借り上げ社宅税制上の扱い給与所得として会社からの住宅補助が『現物給与』とみなされない場合、社会保険料算定の基礎に含まれないことがあります。住宅手当3万円を受け取る場合、所得税や住民税の対象となるため手取りは約2万5千円程度になりますが、借り上げ社宅では税制上のメリットにより、より多くの恩恵を受けられる可能性があります。
03 借り上げ社宅制度を利用するには?

借り上げ社宅制度の利用を検討する際は、対象条件や手続きの流れを事前に把握しておくことが重要です。ここでは実際の利用に向けた具体的なポイントを解説します。
対象となる社員の条件とは
借り上げ社宅制度の対象者は企業によって異なりますが、一般的には以下のような条件が設定されています。
年齢制限では35歳未満の社員に限定する企業が多く、勤続年数については入社から一定期間内という条件を設ける場合があります。また、転勤の有無や役職レベルによって対象が決まることもあるため、事前の確認が必要です。
たとえば、新卒入社から5年間は借り上げ社宅を利用可能で、その後は住宅手当に切り替わるという制度設計の企業もあります。転職を検討する際は、自分がいつまで制度を利用できるかを必ず確認しましょう。
自己負担額と会社負担のバランス
借り上げ社宅における費用負担の割合は、企業の制度設計により大きく異なります。一般的な自己負担率は家賃の20〜30%程度ですが、中には自己負担額を固定金額で設定する企業もあります。
具体的には、家賃10万円の物件で自己負担2万円(会社負担8万円)というケースや、自己負担率25%で2万5千円を負担するケースなどがあります。光熱費については全額自己負担が一般的ですが、一部企業では基本料金を会社が負担するところもあります。
引越し費用や契約の流れも確認しよう
借り上げ社宅制度を利用する際の手続きには、一般的な賃貸契約とは異なる特徴があります。引越し費用については会社が一部負担するケースが多く、特に転勤に伴う引越しでは全額負担する企業もあります。
契約の流れとしては、まず社員が希望物件を選定し、会社の承認を得た後に企業名義で賃貸契約を締結します。この際、審査は企業の信用力で行われるため、個人の信用情報に左右されにくいメリットがあります。
株式会社三央では、このような住宅支援制度を通じて社員の生活安定をサポートし、働きやすい環境づくりに取り組んでいます。
04 借り上げ社宅制度のデメリットや注意点も知っておこう

借り上げ社宅制度には多くのメリットがある一方で、利用前に理解しておくべきデメリットや制約も存在します。制度を最大限活用するために、これらの注意点をしっかりと把握しておきましょう。
転勤・退職時の対応はどうなる?
借り上げ社宅制度における最大のリスクは退職や転勤時の対応です。契約名義が会社であるため、退職と同時に住居を失うことになり、通常は退職後1〜3ヶ月以内の退去が求められます。
転勤の場合は、転勤先でも借り上げ社宅制度が利用できるかどうかで状況が大きく変わります。制度が利用できない地域への転勤では、急な住居確保が必要になる可能性があります。
一定の制約がある場合も
借り上げ社宅では、企業が定めた規則に従う必要があるため、自由度に制限が生じる場合があります。ペットの飼育禁止、同居人の制限、改装・模様替えの禁止など、通常の賃貸契約よりも厳しい条件が設定されることがあります。
また、近隣住民との関係においても、企業の看板を背負っている意識が必要です。騒音やマナー違反などのトラブルが発生した場合、個人の問題だけでなく会社の信用にも影響する可能性があります。
自由な物件選びが難しいケースもある
企業によっては、借り上げ対象物件に家賃上限や立地条件を設定している場合があります。たとえば、家賃上限8万円、通勤時間1時間以内などの制約により、理想的な物件が見つからないケースもあります。
特に人気エリアや新築物件を希望する場合、予算制約により選択肢が限られることがあります。また、会社が提携している不動産会社の物件のみが対象となる場合、一般的な賃貸サイトで見つけた魅力的な物件が利用できないこともあるでしょう。
05 借り上げ社宅制度は"働きやすさ"の一歩

借り上げ社宅制度は単なる経済的支援にとどまらず、社員の総合的な働きやすさ向上に寄与する重要な福利厚生制度です。
福利厚生としての安心感
借り上げ社宅制度があることで、社員は住居に関する不安を軽減し、本業により集中できる環境が整います。特に新入社員や転勤が多い職種では、住居確保の心配をすることなく新しい環境での業務に専念できるメリットがあります。
また、経済的な安定は精神的な余裕にもつながります。住居費の負担が軽減されることで、将来への不安が和らぎ、長期的なキャリアプランを描きやすくなります。
家計へのサポートと暮らしの安定
借り上げ社宅制度による家計への影響は、短期的な節約効果だけでなく、長期的な資産形成にも大きく寄与します。住居費削減により生まれた余裕資金を、資格取得や投資、貯蓄に回すことで、将来的なライフプランがより充実したものになります。
具体的には、月5万円の住居費削減が実現できれば、5年間で300万円の資金を他の用途に活用できます。この資金をスキルアップや将来への投資に使うことで、キャリアアップの機会も広がるのではないでしょうか。
自分らしい住まい選びが可能に
従来の社有社宅と比較して、借り上げ社宅制度では個人のライフスタイルに合わせた住まい選びが可能になります。通勤時間を重視するか、住環境を重視するか、家族構成に合わせた間取りを選ぶかなど、多様な選択肢から最適な住居を見つけられます。
また、転職や結婚などのライフイベントに応じて、柔軟に住まいを変更できる点も大きなメリットです。株式会社三央のように社員一人ひとりの働きやすさを追求する企業では、こうした制度を通じて多様な働き方をサポートしています。
06 まとめ:借り上げ社宅制度を上手に活用して働きやすい環境へ
借り上げ社宅制度は、経済的メリットだけでなく、働く人の生活の質向上と長期的なキャリア形成をサポートする優れた福利厚生制度です。家賃負担の軽減により生まれる経済的余裕は、スキルアップへの投資や将来への備えに活用でき、より充実した職業生活の実現につながります。
株式会社三央では、借り上げ社宅制度をはじめとする充実した福利厚生制度により、社員一人ひとりが安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。住居という生活の基盤をしっかりとサポートすることで、社員が本来の力を発揮し、やりがいを持って働き続けられる職場環境の実現を目指しています。
あなたも理想的な働き方を実現できる環境で、新たなキャリアをスタートしてみませんか。詳しくは株式会社三央の採用情報をご覧ください。









































































































