01 男性の育休制度は本当に使える?現状と制度の基礎を知ろう

男性の育児休業制度は法律でしっかり保障されていますが、実際に育休を取得するかどうかは企業文化や制度への理解度によって大きく左右されます。ここでは、制度の基本的な仕組みと、男性が育休を取得する際に知っておきたい背景について詳しく解説します。
男性が育児休業を取得する背景と社会の変化
現代社会では共働き世帯の増加に加え、父親も積極的に育児に関わりたいという意識が高まりつつあります。厚生労働省の調査によると、男性の育児休業取得率は2023年度に30.1%と過去最高を記録し、年々着実に上昇しています。
この背景には、働き方改革の推進や男女共同参画社会の実現に向けた国の取り組みがあります。企業側でも、優秀な人材の確保・定着を図るため、男性社員が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を進めています。具体的には、取得を促す社内制度の整備や、復帰後の業務フォロー体制の構築といった支援策が広がっています。
育児介護休業法と「産後パパ育休」の違いとは
2022年に改正された育児介護休業法により、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新たに創設されました。これは従来の育児休業とは別枠で、子どもの出生後8週間以内に、原則最大28日間(4週間)を2回に分けて取得できる制度です。
一方、通常の育児休業は子どもが1歳になるまで取得可能で、一定の条件を満たせば最長2歳まで延長できます。父母それぞれが育児休業を取得できるため、両親が協力し合いながら育児に取り組む体制が整えやすくなっています。
産後パパ育休の大きな特徴は、事前申請の期限が従来の1か月前から2週間前に短縮されたことで、出産のタイミングに合わせてより柔軟に取得しやすくなった点です。
制度上の取得条件と企業ごとの違い
育児休業を取得するには、いくつかの条件があります。基本的には、同じ会社に継続して雇用されており、育休終了後も引き続き勤務が見込まれることが必要です。
また、企業によっては法定制度に加えて、独自の支援制度を設けていることもあります。たとえば株式会社三央では、法令に準じた育休制度を整備し、男女ともに育児休業の取得実績があります。
こうした環境は、長く安心して働ける職場づくりの一環といえるでしょう。転職や就職活動の際は、育休の取得実績や制度内容についても確認しておくことが大切です。
02 育休の取得期間と給与はどうなる?リアルな数字で解説
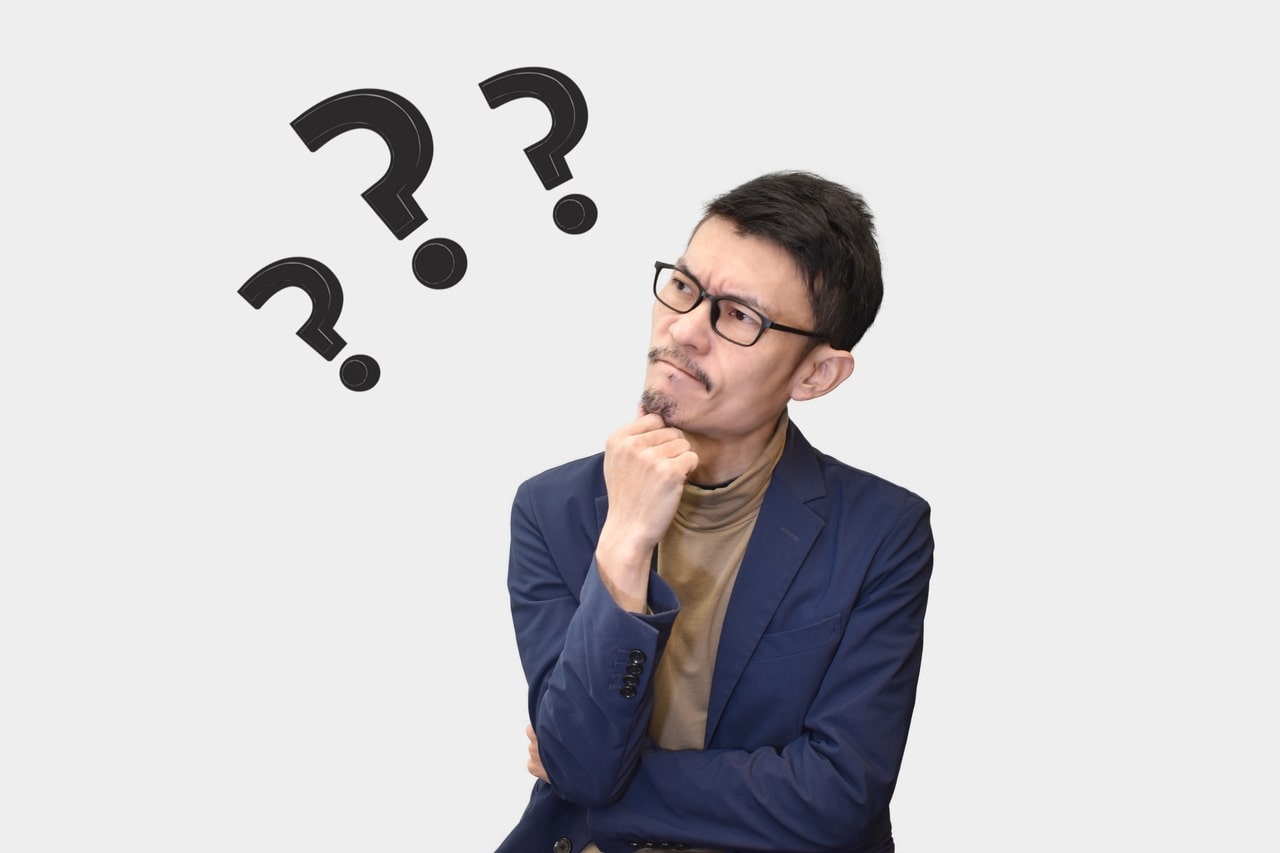
育児休業を取得する際に、多くの方が気にするのは「取得期間」と「収入への影響」です。ここでは、育児休業中に受け取れる給付金の仕組みや、実際に家計にどのような影響があるのかを、具体的な数字を交えてわかりやすく解説します。
男性育休の平均取得期間と実態
男性の育児休業の平均取得期間は約46日と、女性の約11か月に比べて大幅に短いのが現状です。取得の傾向としては、出産直後の1~2週間程度の短期取得が最も多く、次いで1~3か月程度の中期取得が続きます。
職種によって取得傾向に差が出ることもあります。たとえば、技術系職種では業務の計画調整がしやすいため比較的長期の育休取得が可能な傾向がある一方で、営業職などでは引き継ぎの難しさから短期間の集中取得にとどまるケースが多いといわれています。これは業務内容や職場の体制によっても左右されるため、企業ごとの取り組みも重要なポイントです。
育休中の給与・給付金の仕組み(育児休業給付金)
育児休業中の収入は、主に雇用保険から支給される「育児休業給付金」が支えています。給付額は休業開始時の賃金日額の67%(育休開始から180日を過ぎると50%)が基本で、支給上限額は年度ごとに変動します。2024年度の上限は、67%の場合で月額約31.8万円です。
例えば、月収30万円の方が6か月間育休を取得した場合、最初の180日間は月約20万円、残りの期間は月約15万円の給付金を受け取ることができます。さらに、育休中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りの減少は予想よりも少なくなるケースが多いです。
家計と両立できる?金銭面での注意点と準備
育休の取得を検討する際には、家計の収支を事前に見直し、生活費の備えをしておくことが重要です。育児休業給付金の初回支給は申請から約2か月後になるため、それまでの生活費を確保しておくと安心です。
なお、育児休業給付金は非課税ですが、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休中も支払いが発生します。また、住宅ローンや保険料などの固定費は変わらず続くため、月ごとの支出を正確に把握しておきましょう。
一方、育児に必要なおむつ代やミルク代は増えるものの、通勤費や外食費が抑えられる場合もあります。家計簿アプリなどを活用して、収支を可視化し、育休中の生活をシミュレーションすることが有効です。
03 男性が育休を取得しても出世に影響しない?キャリアとの両立を考える

男性が育休を取得すると「キャリアに悪影響が出るのでは」と不安に感じる方は少なくありません。そこで、実際の復帰事例や企業が整えているフォロー体制について詳しく紹介します。安心して育休を取得し、復帰後もスムーズに働ける環境づくりが進んでいます。
育休取得後の復帰とキャリア形成の可能性
男性が育児休業を取得した後も、職場に復帰して活躍を続けているケースは少なくありません。実際に、技術職や企画職などでは、育休取得を経た社員がプロジェクトの中心メンバーとして活躍する事例も見られます。
こうしたキャリア継続の背景には、本人のスキル維持への意識や、企業側のサポート体制が関係しています。たとえば、復帰後の研修制度や、柔軟な働き方への対応が整っている企業では、育休からのスムーズなキャリア再開が実現しやすくなります。
株式会社三央では、社員一人ひとりの主体的な成長を重視する風土があり、育児休業からの復帰後も継続的にキャリアを築けるような環境づくりに取り組んでいます。こうした企業の姿勢に加え、個人の学びや準備も組み合わせることで、育休取得後もキャリアを止めずに活躍し続けることが可能になります。
上司や同僚との関係性、チーム体制の工夫
育休取得をスムーズに成功させるためには、事前のコミュニケーションが非常に重要です。まず、育休の取得予定を早めに上司に相談し、業務の引き継ぎ計画を綿密に立てることで、チーム全体の理解と協力を得やすくなります。
具体的には、以下のような準備が求められます。
・業務マニュアルの整備
・進行中プロジェクトの状況共有
・緊急時の連絡体制の構築
さらに、復帰時期についても柔軟に調整できるよう、上司との定期的な連絡を維持することが推奨されます。
優良企業では、育休取得者の業務を複数人でカバーできる体制を整備し、特定の個人に依存しない業務プロセスの構築を進めています。これにより、誰もが安心して育休を取得できる職場環境が実現されているのです。
評価制度や人事面のフォロー体制
育児休業を取得したことを理由に不利益な扱いを受けることは、法律で明確に禁止されています。特に、育児・介護休業法では、育休を取得した社員に対して解雇や不当な評価を行うことは違法とされています。
実際の評価制度においても、多くの企業では育休中の期間を評価対象から外し、復帰後の成果に基づいて公正な評価を行う仕組みを整えています。
また、復帰をスムーズにするために「段階的な業務復帰制度」を設ける企業も増えており、時短勤務から段階的に通常勤務へ移行できるなど、育児と仕事の両立を支援する体制が整いつつあります。
昇進や昇格についても、育休取得によってキャリアが不利にならないよう、成果主義に基づいた公平な評価を目指す企業が高く評価されています。
このように、評価制度や復帰支援が整っているかどうかは、育休取得後のキャリアにも大きく関わります。次に、男性が育休を取得しやすい企業にはどのような特徴があるのかを見ていきましょう。
04 育休を支援する企業は増加中|企業規模を問わず広がる取り組み
近年、男性の育児休業を支援する企業は、業界や規模を問わず着実に増えてきています。大手企業のみならず、育児と仕事の両立を重要な経営課題と捉え、制度整備や職場風土の改善に取り組む中堅企業やベンチャーも少なくありません。特に、若手人材の定着や多様な働き方の実現を重視する企業では、男性の育休取得を積極的に後押しする動きが加速しています。
では、実際にどのような企業が「育休を取得しやすい職場」として取り組みを進めているのでしょうか?次に、その見分け方のポイントをご紹介します。
実績や事例を公表している企業の見分け方
信頼できる企業を見分けるポイントとして、まずは具体的な取得実績の公表が挙げられます。たとえば、採用サイトや企業の公式ホームページで「男性の育休取得率」「平均取得期間」「復帰後のキャリア事例」などを明示している企業は、制度が実際に機能している可能性が高いと判断できます。
さらに、第三者機関による認定も重要な指標です。厚生労働省の「くるみん認定」や、より基準の厳しい「プラチナくるみん認定」を取得している企業は、育児支援制度が一定の基準をクリアしていることを公的に証明されています。
面接の際には、具体的な質問をすることも効果的です。たとえば、「男性社員の育休取得事例はありますか?」「育休後の復帰支援やフォロー体制はどのようになっていますか?」など、具体的な回答が得られる企業は、制度の運用や職場の理解が進んでいると判断でき、信頼度が高いと言えるでしょう。
福利厚生や職場文化で選ぶ企業選びの視点
男性育休の取得しやすさは、企業の職場文化や経営理念に大きく左右されます。たとえば、「社員も会社も一緒に成長していきたい」という考えを持つ企業では、個人のライフステージの変化をポジティブに捉え、育休取得を成長の一環として支援する傾向があります。
また、柔軟な働き方の選択肢が豊富な企業は育児と仕事の両立をより実現しやすくなります。具体的には、育休のほかに時短勤務、在宅勤務、フレックスタイム制度などが整備されていることが重要です。これらの制度が整っている企業では、復帰後も無理なく働ける環境が整っているため、男性育休の取得が長続きしやすいと言えます。
さらに、研修制度の充実も見逃せないポイントです。復帰後のスキルアップ支援やキャリア開発プログラムが整っている企業では、育休取得がキャリアの断絶ではなく、新たな成長段階として位置づけられています。こうした企業は、育休取得者のキャリア形成を積極的に後押ししていると言えるでしょう。
05
企業選びで後悔しないために|働きやすさと家族への配慮を両立するには

長期的に企業を選ぶ際には、育休制度の充実だけでなく、総合的な「働きやすさ」をしっかり評価することが大切です。家族との時間を大切にしつつ、安心してキャリアを築ける環境を見極めるポイントを詳しく解説します。
育休制度と合わせて注目したい制度(時短勤務・在宅など)
育休制度の充実度に加え、復帰後の働き方の柔軟性も企業選びの重要なポイントです。具体的には以下の点を押さえておくとよいでしょう。
時短勤務制度の柔軟性
・法定の「子どもが3歳まで」という期間を超え、小学校入学まで利用可能な企業は育児継続支援の観点から理想的です。
・ 時短勤務時間についても段階的に調整できる制度があると、ライフステージや業務状況に応じて無理なく働けます。
在宅勤務制度の運用条件
・週あたりの在宅勤務可能日数や対象業務の範囲を確認しましょう。
・技術系職種では、CAD設計や研究開発の一部を在宅で行えるケースが増加しています。
フレックスタイム制の特徴
・コアタイム(必ず勤務が必要な時間帯)と調整可能な時間帯を把握し、自身の生活リズムや育児負担に合わせて働き方を選べるかがポイントです。
企業の制度を検討する際は
・時短勤務の利用可能期間や時間帯の細かい選択肢
・在宅勤務の頻度や業務範囲
・フレックスタイムの具体的な運用ルール
これらをしっかり確認し、自分のライフスタイルにマッチするかどうかを見極めることが大切です。これにより、育児と仕事の両立を無理なく続けられる環境を選ぶことができます。
「家族も仕事も大切にしたい」あなたに合う企業とは
家族との時間を大切にしつつ、仕事での達成感も求める方には、成果主義を採用している企業がおすすめです。以下のポイントが特に重要です。
成果主義による評価
働く時間ではなく成果で評価される環境では、効率的に業務を進めることで無駄な残業を減らし、家族との時間を確保しやすくなります。
専門性を活かせる職種
技術営業、機械設計、フィールドエンジニアリングなど、個人のスキルや経験が直接評価される専門職は、育休などのライフイベントがあってもキャリアの継続性を維持しやすい特徴があります。
長期的なキャリア形成支援
たとえば、能力評価に基づく昇給・昇格制度や、育休後の職場復帰を支える人事体制が整っている企業では、ライフステージの変化にも柔軟に対応できます。
こうした特徴を持つ企業の一例として、株式会社三央のように、専門性を生かせる職場でありながら、社員のライフイベントに配慮した制度づくりに力を入れている企業もあります。家庭と仕事、どちらも大切にしたい方にとって、長く働ける環境といえるでしょう。
06 福利厚生から見る「働きやすさ」──三央の取り組み
就職や転職活動において、給与や職種だけでなく、福利厚生の充実度が企業選びの大切な判断基準になっています。近年は、長期的なキャリア形成や家庭との両立を見据えて、住宅補助や休暇制度、各種保障制度といった“働きやすさ”を支える制度に注目が集まっています。
こうした中、三央でも、社員が安心して長く働けるような環境づくりに力を入れています。たとえば、借り上げ社宅制度により、ライフスタイルに合わせた住環境の選択を支援。加えて、努力や成果が評価される業績賞与制度や、将来に備えた退職金制度・長期所得補償保険など、生活とキャリアの両面をサポートする福利厚生を整備しています。
これらの制度は、社員一人ひとりの人生設計に寄り添うものであり、育児休業の取得や職場復帰を支える土台にもなっています。三央では、制度を「形だけ」で終わらせることなく、実際に活用しやすいよう風土や運用の整備にも取り組んでいます。
男性社員の育休取得実績と取得期間の目安
近年、男性社員の育児休業取得に対する社会的理解が進み、企業でも実際に取得するケースが増えてきました。社内制度や風土が整っている職場では、育休を前提とした業務の引き継ぎや、復帰後のサポート体制が整っており、男性社員が安心して休業に入れる環境づくりが進んでいます。
育休の取得期間は個人や職種によって異なりますが、多くの場合、1~2週間の短期取得または1~3か月の中期取得が主流です。出産直後のサポートを目的とした「産後パパ育休(出生時育児休業)」を活用し、2回に分けて取得するケースも見られます。
実際の企業事例として、技術系の専門職が多数在籍する株式会社三央では、産休・育休取得後の職場復帰率は100%を維持しています。(2025年7月時点)社員全体の育休取得割合は、男性割合がやや多いため男性が約67%、女性が約33%で、男性の取得も一般的なものとなっています。三央では社員一人ひとりのキャリアとライフイベントの両立を支える体制が整っており、育休後も自分らしく働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。
企業を選ぶ際は、制度の有無だけでなく、「実際に取得された実績があるか」「どの程度の期間取得されているか」といった情報にも注目すると、働きやすさの具体的なイメージがつかめるでしょう。
三央の長く安心して働ける職場環境と柔軟な働き方の整備
株式会社三央では、能力等級制度により、年齢や勤続年数に関係なく実力を正当に評価する環境が整っています。30歳までは毎年の昇給が保障されており、31歳以降は能力評価に基づいて賃金が決まる仕組みとなっているため、家族計画を立てやすく安心できる制度です。
また、借り上げ社宅制度では、社員が自由に選んだ物件に対して会社が家賃補助を行うため、家族のライフスタイルに合わせた住環境を選択できます。業績賞与制度も導入されており、頑張った分が適切に評価される仕組みは、育休復帰後のモチベーション維持にもつながっています。
※一部諸条件がございます
同社が求める「自律型社員」とは、企業の一員として能動的に考え、常に問題意識を持って改善に努める人材のことです。この考え方は育児と仕事の両立においても重要であり、社員が自分らしい働き方を主体的に選び、家族との時間と専門性の向上を両立できる環境を提供しています。
07 まとめ|育休は「取れるか」ではなく「取ってどう働くか」が問われる時代へ
男性の育児休業制度は、法制度の整備や社会の意識変化により、取得しやすい環境へと着実に進化しています。重要なのは、制度があることを知るだけでなく、実際に活用できる企業を選ぶことです。
給与面では育児休業給付金によって一定の収入が確保でき、事前の家計管理を行うことで経済的な不安も軽減できます。キャリアについても、適切な企業選びと準備によって、育休をキャリアの中断ではなく成長の機会として活用できることが分かっています。
企業を選ぶ際は、制度の有無だけでなく、実際の取得実績や復帰後のフォロー体制、職場文化を総合的に評価することが大切です。福利厚生の充実度や働き方の選択肢の多さも、長期的な視点では欠かせません。
これからの時代は、育休を「取得できるかどうか」ではなく、「取得していかに家族との時間と仕事の成長を両立させるか」が問われています。株式会社三央のように、社員の長期的な成長と幸福を重視する企業では、男性の育休取得も自然な選択肢として受け入れられ、家族も仕事も大切にできる働き方が実現されています。
専門性を活かしながら家族との時間を大切にしたい方は、ぜひ株式会社三央で自律型社員として共に成長しませんか。技術力と人間力を兼ね備えた人材を求めており、充実した福利厚生制度のもと、長く安心して働ける環境が整っています。詳しくは採用サイトをご覧ください。








































































































