01 OJTとOFF-JTの概要:意味と目的

OJT(On-the-Job Training)とOFF-JT(Off-the-Job Training)は、企業が新入社員や既存社員のスキル向上を図るための代表的な研修手法の1つです。実際の業務を通じて学ぶOJTと、業務から離れた場所で行う座学研修のOFF-JTは、それぞれ異なる特徴と効果を持っています。
現代の企業では、この2つを組み合わせた研修体系を構築することで、効果的な人材育成を目指している傾向があります。多くの企業がどちらか一方ではなく、両方を活用した総合的な教育プログラムを展開しており、新入社員の早期戦力化と長期的な成長支援を実現してると考えられます。
02 OJTとは何か:定義と期待効果

OJTとは「On-the-Job Training」の略称で、実際の職場で業務を遂行しながら行う実践的な教育訓練のことです。先輩社員や上司が指導者となり、日常業務を通じて必要なスキルや知識を身につけていく手法です。
例えば、新入社員が先輩と一緒に顧客先を訪れたり、プロジェクトに参加しながら業務の流れを学んだりするケースがあります。株式会社三央では、「会社も社員も共に成長する」という方針のもと、入社後の教育体制に注力しており、実務を通じて幅広い知識を吸収できる環境づくりを進めています。
OJTの一例としては、実践を通じてスキルを身につけやすいことや、職場の雰囲気や企業文化を自然に理解しやすい点が挙げられます。また、業務と直結した学びが可能なため、早い段階で戦力として活躍できる可能性があります。
03 OFF-JTとは何か:座学研修の特徴
OFF-JTとは「Off-the-Job Training」の略称で、通常の業務から離れた場所で実施される集合研修や座学形式の教育訓練を指します。研修室や外部の研修施設において、講師による講義や演習、グループワークなどを通じて知識やスキルを習得します。
研修の一例としてはビジネスマナー研修、コンプライアンス研修、業界知識の習得などが挙げられます。OFF-JTでは、体系的な知識を効率よく身につけられるとされ、同期入社の仲間とともに学習することで横のつながりが深まることもあるでしょう。
株式会社三央では、入社時期から社員の成長フェーズに合わせた研修プログラムを用意し、事業領域や業務内容に不慣れな人でも安心して学べる環境づくりに配慮しています。OFF-JTの特徴としては、基礎知識を落ち着いて習得でき、業務に追われずに学習に集中しやすい点が挙げられます。
04 OJTとOFF-JTの違い:実施場所と学習主体の比較

OJTとOFF-JTの主な違いを以下の表で比較します
| 項目 | OJT | OFF-JT |
| 実施場所 | 実際の職場 | 研修室・外部施設 |
| 学習方法 | 実践を通じた経験学習 | 講義・演習による理論学習 |
| 指導者 | 先輩社員・上司 | 専門講師・人事担当者 |
| 学習内容 | 実務に直結したスキル | 体系的な知識・理論 |
| メリット | 即戦力化、職場適応 | 基礎固め、同期との結束 |
| デメリット | 指導者により質が左右される | 実践力に直結しにくい |
OJTは個別指導が中心となるため、指導者のスキルや教える能力によって学習効果が大きく左右される可能性があります。一方、OFF-JTは標準化された内容を学べるため、全社員が同じレベルの基礎知識を身につけることが期待できます。
株式会社三央では、オールマイティに活躍可能なマネジメント能力の高い社員を育成していく方針により、社員一人ひとりに任せる業務の範囲が幅広く、OJTとOFF-JTの両方を効果的に活用した人材育成を行っています。
05 OJTを効果的に進めるステップ
OJTを成功させるためには、計画的なアプローチと継続的なフォローアップが重要です。適切な目標設定から振り返りまで、段階的に進めることで学習効果を最大化できる可能性があります。
目標設定とKGI/KPIの立て方
OJTを効果的に進めるためには、明確な目標設定が不可欠です。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)として「3ヶ月後に独立して顧客対応ができるようになる」といった最終目標を設定し、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)として「週に5件の顧客訪問同行」「月末までに基本的な商品知識テストで80点以上取得」などの中間指標を設定します。
具体的には、新入社員の習熟度に応じて段階的な目標を設定し、達成度を定期的に評価します。株式会社三央では、大型プラントに関する知識を中心に、実際の業務を通して多くの知識を学ぶことができる環境があり、先輩や上長からのフィードバックも行っています。目標設定では、新入社員の強みや興味関心も考慮し、個人に合わせたカスタマイズが重要になると考えられます。
実践指導からフィードバック、振り返りまで
OJTの一例としては、「見せる→やらせる→確認する」という三段階のステップが用いられることがあります。まず指導者が実際の業務を見せ、その後新入社員が実践し、最後に成果を確認してフィードバックを行う流れです。また、日々の振り返りで学んだことや成功・改善点を整理し、次の学習計画に反映させる方法も見られます。
週次や月次で定期的に面談を設け、進捗や課題、今後の方向性を話し合うケースもあるようです。株式会社三央では、研修だけでなく日常業務を通じたスキルアップ機会を用意し、継続的な成長を支援する仕組みが整えています。フィードバックは具体的かつ建設的に行われるように心がけており、新入社員のモチベーション維持にも配慮しています。
06 OJTカリキュラム例
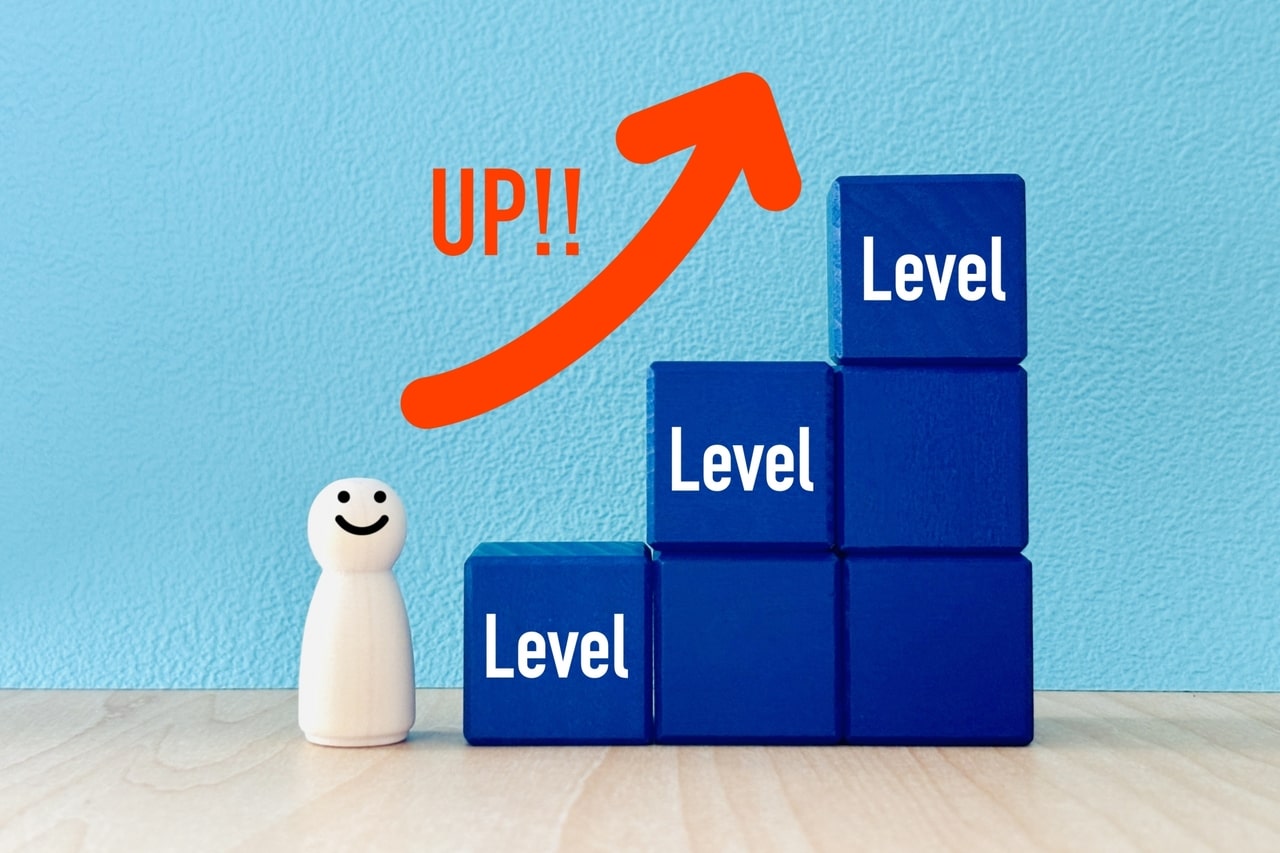
あくまで一例として、OJTカリキュラムを期間ごとに段階的に区切って設計する方法が考えられます。たとえば、最初の週は職場環境への慣れと基本業務の理解に時間を割き、その後の2〜4週目で指導者と並走しながら実務を通じた学習を進めるケースがあります。続く2か月目には、担当する業務の一部を自分で実行しつつ、定期的なフォローアップ面談を設けるパターンもあります。そして3か月目には、これまでの学びを踏まえて総合的な業務遂行能力の向上を図り、評価や振り返りを行う流れが参考になるかもしれません。
| 期間 | 主な学習内容 | 目標 |
| 1週目 | 職場見学・基本ルール理解 | 職場への適応 |
| 2-4週目 | 先輩同行・基本業務習得 | 基礎スキル身につけ |
| 2ヶ月目 | 一部業務の独立実行 | 実践力向上 |
| 3ヶ月目 | 総合業務・評価フィードバック | 独り立ち準備 |
株式会社三央では、機械設計(CAD)、フィールドエンジニアリング(施工管理、電気制御)、技術営業、技術研究開発、整備工など多様な職種において、それぞれの特性に応じたOJTカリキュラムを設計し、新入社員が着実に成長できる環境を提供しています。
07 まとめ
OJTとOFF-JTは、それぞれ異なる特徴や効果を期待できる研修手法の一例と考えられます。たとえば、OJTでは実践を通じてスキルを習得しやすい一方、OFF-JTでは座学やワークショップで体系的な知識を効率的に学べるケースがあるようです。最近では、両者を組み合わせた育成プランを導入している企業も少なくないようです。
就活中の皆さんが企業を選ぶ際には、研修制度の内容やOJTの指導体制、フォローアップの仕組みがどの程度整備されているかを確認してみるとよいかもしれません。また、自分の学び方や成長志向に合ったプログラムが用意されているかどうかも、入社後のスキルアップを見込むうえでの参考になるでしょう。
たとえば、株式会社三央ではグループ企業として一定の安定感を保ちながら、実務を通じた学習機会と定期的なフィードバックを組み合わせる仕組みづくりに力を入れています。こうした環境づくりで自律的に学びたい方の成長を後押しができる企業でありたいと願っています。








































































































