01 電気電子工学科出身者におすすめの就職業界

電気電子工学科で学んだ専門知識は、インフラ、製造、通信、エネルギーなど多様な業界で活かすことができます。特に技術革新が進む近年では、電子・電気系の人材が社会の基盤を支える重要な存在として期待されています。以下では、電気電子系出身の新卒者が活躍できる代表的な業界とその特徴を紹介します。
プラント・インフラエンジニアリング業界の特徴
社会インフラの老朽化やカーボンニュートラルへの対応が進む中、プラントやインフラ施設の設計・保全を担う業界のニーズが高まっています。電気電子工学の知識を活かし、制御盤の設計、設備の電気系統図作成、現地での試験調整業務などに携わることが可能です。
たとえば、株式会社三央のような企業では、配電・制御システムの開発から現場での動作確認・据付調整まで幅広く経験できる環境があり、技術の基礎と実践力をバランス良く高められるフィールドとなっています。
電力・エネルギー業界の特徴
電力・エネルギー業界は、社会基盤を支える安定性の高い分野です。近年では再生可能エネルギーやスマートグリッドの導入が進み、次世代電力システムの構築に貢献できる機会が増えています。
新卒者は、発電設備の保守・監視、送配電ネットワークの保全、太陽光・風力発電システムの設計補助などに関与し、電気系統全体を俯瞰できるスキルが養われます。
半導体・家電メーカー業界の特徴
半導体や家電製品の分野では、回路設計・組込制御など電気電子工学の知識が直結する業務が多くあります。特にIoTやAI搭載家電の拡大により、先端技術への対応力が求められています。
新卒者は、アナログ・デジタル回路設計、試作検証、量産設計、品質管理などを経験しながら、ものづくりの上流から下流まで幅広い工程に関わることができます。
自動車・FA(ロボット)業界の特徴
自動車業界では、電動化・自動運転技術の進化により、電気電子系人材のニーズが拡大しています。車載電子機器、バッテリー制御、センサー処理など幅広い技術領域で活躍が可能です。
また、FA(ファクトリーオートメーション)分野では、産業用ロボットや自動化装置の制御システム開発に関わることができ、制御工学や組込システムの知識を活かせる現場が豊富です。
通信インフラ・IoT業界の特徴
通信インフラ・IoT分野は、5Gの普及やスマートデバイスの拡大によって、今後も成長が期待される分野です。基地局設計や通信機器のファームウェア開発、センサーネットワークの構築など、通信と制御を横断する技術力が求められます。
加えて、株式会社三央のようなプラント系企業でも、IoTを活用した設備モニタリングや遠隔制御の導入が進んでおり、通信スキルを持つエンジニアの活躍の場が広がっています。
02 主な職種と業務内容
 電気電子工学科出身の新卒者が携わる職種は多岐にわたり、それぞれ異なる専門性や現場ニーズに応じた役割が存在します。大学での専攻や卒業研究の内容をもとに、自身の興味や適性に合った職種を見極めることが、キャリアの第一歩となります。
電気電子工学科出身の新卒者が携わる職種は多岐にわたり、それぞれ異なる専門性や現場ニーズに応じた役割が存在します。大学での専攻や卒業研究の内容をもとに、自身の興味や適性に合った職種を見極めることが、キャリアの第一歩となります。
回路・基板設計エンジニア
回路・基板設計エンジニアは、アナログ・デジタル回路の知識を基盤に、電源回路や信号処理回路の設計・評価に携わります。新卒者は、CADツールの操作や設計基準の理解から始まり、徐々に実際の設計作業に取り組むようになります。大学で回路設計に関する研究経験がある場合、その知識を応用しやすい分野といえます。
組込ソフト・ファームウェア開発エンジニア
組込ソフト・ファームウェア開発の業務では、マイコン制御や周辺機器との通信制御などが求められます。新卒者は、C言語やアセンブリを使った基本的なプログラミングや、センサー処理、通信プロトコルの実装補助といった業務から経験を積みます。ハードウェアに近い層のソフト開発に関心がある学生にとっては、大学で学んだ基礎知識を実践的に活かしやすい職種です。
制御システム設計エンジニア
制御システム設計の分野では、PLC制御やセンサ入力に基づく自動化処理の設計など、装置や設備の動作を制御する技術が中心となります。新卒者は、制御理論の理解に加えて、実際の設備に触れながら制御ロジックの設計補助から始めるケースが一般的です。
試験評価・品質保証エンジニア
この職種では、製品や部品が規格を満たしているかを確認するための測定や環境試験を行います。新卒者は、電気的特性の測定方法や各種試験装置の扱い方を習得し、温度試験・EMC試験・耐久評価などを担当します。品質データの分析や改善提案など、論理的に考察する力が活かされる職種です。
保全・メンテナンスエンジニア
保全・メンテナンスエンジニアは、生産現場やインフラ設備の安定稼働を支える役割を担います。新卒者は、日常点検や基本的な修理対応を通じて、機器の構造理解とトラブル対応力を身につけていきます。一定の現場経験を重ねることで、設備の状態変化を予測し、予防保全や効率化の提案といったより高度な業務にも関われるようになります。
03 必要スキル・資格と学習方法

新卒の就職活動では、大学で学んだ基礎知識に加え、実務に直結するスキルや知識の習得が評価される傾向にあります。必須とされる資格は少ないものの、保有していると選考で有利になるものや、入社後の実務理解を助けるものもあるため、在学中から段階的に準備を進めておくことが、自信と選択肢につながります。
電気主任技術者/電気工事士資格取得
電気主任技術者や電気工事士は、電気設備の設計・管理・保守などに携わる職種で特に評価されやすい国家資格です。特にインフラや設備系の業界を志望する場合、保有していると採用時に有利に働くケースがあります。
第三種電気主任技術者や第二種電気工事士は、在学中でも受験可能であり、合格すれば基本的な電気理論や安全知識を証明する手段として有効です。ただし、実務に直結する業務を行うには一定の実務経験や実技スキルが求められるため、早めの学習計画が効果的です。
プログラミング(C/C++/MATLAB/PLC)
近年の電気電子系の開発現場では、ハードウェアとソフトウェアの融合が進んでおり、プログラミングスキルの有無が選考で評価される傾向があります。
C/C++は組込み系ソフトウェア開発、MATLABは信号処理・シミュレーション、PLCはFA制御・自動化装置の分野で活用されています。大学での授業や卒業研究に加え、個人制作や研究室活動を通じて、実践的なスキルを磨いておくと就職活動での強みになります。
また、GitHubなどでコードを整理・公開することで、自身の技術力をポートフォリオとして可視化する方法も有効です。
CADツール(AutoCAD/EAGLE)の習得
CADツールは、回路設計や配線図作成など設計関連職種において頻繁に使用されるツールであり、学生のうちに基礎操作を習得しておくことは大きなメリットになります。
AutoCADは建築・機械・電気配線設計など幅広い用途があり、EAGLEは電子回路基板(PCB)設計に特化しています。授業や研究室での使用に加えて、個人プロジェクトやオープンソースデータを参考に応用力を身につけると、即戦力としての期待も高まります。
学生版ライセンスや教育用プラットフォームを活用することで、在学中から実用的なスキルを着実に磨くことが可能です。
04 キャリアパスモデルと年収相場
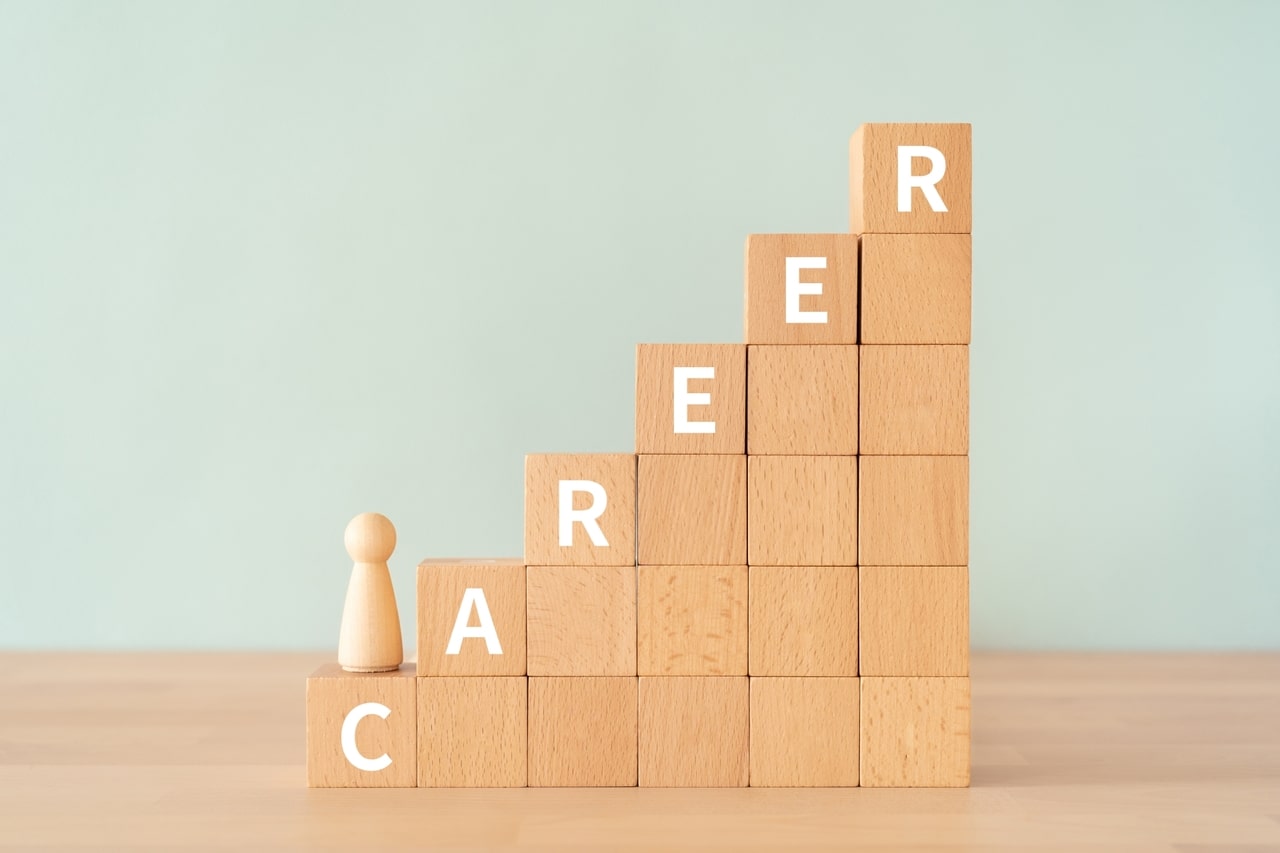
電気電子工学科出身の新卒者は、頑張り次第で専門性を活かして着実にステップアップできるキャリアパスを描くことが可能です。技術領域の広がりにより、多様な職種や分野で活躍できる環境があり、長期的なキャリア形成を見据えて、自分に合った道を選ぶことが重要です。
初任給~5年目の年収レンジ
電気電子系エンジニアの初任給は、年収330万円〜420万円程度からのスタートが一般的です。経験を積むことで徐々に収入も上昇し、以下のようなレンジが一つの目安となります。
- 1年目(新卒):年収330万~420万円
- 3年目:年収370万~500万円
- 5年目:年収400万~600万円
※地域・業種・企業規模により幅あり
株式会社三央のように、技術者の成長を支援する研修制度や等級制度が整っている企業では、経験や成果に応じて昇給・賞与の評価を受けられるため、実力を着実に反映できる環境が整っています。
専門職・管理職への昇進イメージ
新卒入社後は、担当エンジニア(ジュニアレベル)としてキャリアをスタートし、経験や実績を重ねることで徐々に責任ある役割を担うようになります。
一般的な成長ステップの一例
- 3~5年目:シニアエンジニア/担当分野の主担当
- 7年目以降:プロジェクトリーダー、技術責任者など
- 10年目以降:管理職や高度専門職への昇格機会
専門分野を深めていく道と、マネジメント能力を発揮する道のいずれも目指すことができ、会社の制度や評価体制を活用しながら自分に合ったキャリア構築が可能です。
部署異動・ジョブローテーション例
若手技術者の成長支援を目的に、複数部門を経験するジョブローテーションを取り入れる企業も増えています。設計、製造、品質管理、営業技術など、異なる視点を持つ経験を積むことで、より実践的な技術力と課題解決力を育むことができます。
05 就活対策ガイド

新卒の就職活動を成功させるためには、電気電子工学科の専門性を効果的にアピールする戦略的なアプローチが重要です。学生時代の学習成果と研究経験を適切に整理し、企業が求める人材像とのマッチングを図ることが内定獲得の鍵となります。
ES作成:技術的強みの伝え方
エントリーシート(ES)では、大学での学習内容と研究経験を具体的に記述することが重要です。たとえば、「卒業研究において○○の課題に取り組み、△△の手法を用いて▲▲の成果を得た」といった具体的な表現を心がけます。研究室での実験やプロジェクト経験、授業で学んだ理論の応用例などを交えて、技術的な理解度と問題解決能力をアピールします。専門用語は適度に使用し、技術系以外の採用担当者にも理解しやすい表現を意識することが大切です。
面接対策:技術質問&回答例
新卒の技術面接では、基礎知識の確認から学生時代の研究内容まで幅広い質問が予想されます。「オームの法則について説明してください」「あなたの研究テーマの意義は?」などの基本的な質問から、「この回路図の動作を説明してください」といった応用問題まで対策が必要です。回答の際は、理論的な説明に加えて研究室での実験経験や授業での学習体験を交えることで、理解の深さと学習意欲をアピールできます。
グループディスカッションのポイント
グループディスカッションでは、技術的な知識を活かしつつ、チームワークとコミュニケーション能力を示すことが重要です。他の参加者の意見を尊重しながら、自分の専門知識を適切なタイミングで提供します。論理的な思考プロセスを明確に示し、建設的な議論をリードする姿勢が評価されます。株式会社三央のような技術者集団では、専門性とコミュニケーション能力のバランスが特に重視されるため、日頃から両方の能力を磨いておくことが重要です。
企業研究で押さえておきたい業界動向
企業研究を行う際は、業界全体の動きやトレンドを把握したうえで、各企業の技術的な特徴や強みに注目することが重要です。電気電子工学の分野では、IoTやAI、自動化技術といったテーマが近年注目を集めており、多くの企業がこれらを取り入れた製品・サービスの開発に取り組んでいる傾向があります。
また、環境・エネルギー関連の分野では、カーボンニュートラルや再生可能エネルギーへの対応を背景に、持続可能な社会の実現に向けた技術開発が広がりつつあります。こうした動向に目を向けることで、企業が目指す方向性や社会的な役割への理解が深まり、志望動機をより説得力のある形で表現しやすくなります。
06 最新技術トレンド
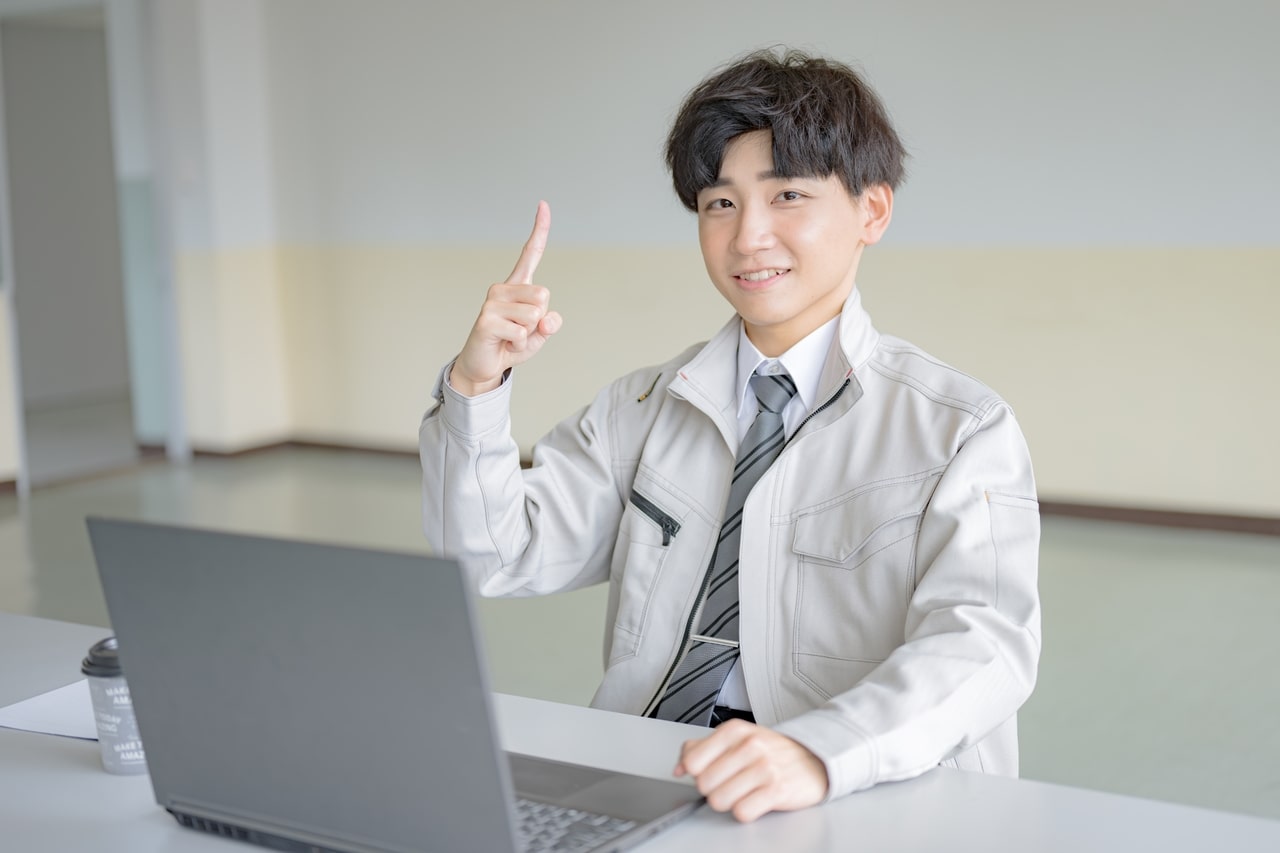
電気電子工学分野では技術革新が急速に進んでおり、最新のトレンドを把握することで将来性の高いキャリアを構築できます。これらの技術分野は今後も成長が期待され、新卒者にとって魅力的な就職先となっています。
EV/自動運転技術の最前線
電気自動車(EV)と自動運転技術は、自動車業界の大きな変革をもたらしており、新卒採用も活発化しています。EV分野では、バッテリー管理システムや充電制御技術の開発が重要な領域となっています。自動運転では、センサー技術、画像処理、制御アルゴリズムなどの統合的な技術が求められます。たとえば、LiDARやカメラからの情報を処理し、リアルタイムで車両制御を行うシステムの開発などが主要な技術課題で、新卒者でも基礎研究から携わる機会があります。
スマートファクトリーとIoT導入事例
製造業では、IoT技術を活用したスマートファクトリーの実現に向けて新卒エンジニアの採用を強化しています。センサーネットワークによる設備監視、予防保全システム、生産データの解析などが主要な技術要素です。具体的には、機械学習を用いた故障予測システムや、リアルタイム品質管理システムなどの開発に新卒者も参画できます。株式会社三央のような設備レンタル事業においても、IoTを活用した遠隔監視システムの開発に新卒エンジニアが貢献する機会が増えています。
再生エネルギー・AI組込システム
再生可能エネルギーの普及に伴い、AI技術を組み込んだ効率的な発電・蓄電システムの開発に新卒者の参画機会が拡大しています。太陽光発電の発電量予測、風力発電の最適制御、エネルギー貯蔵システムの管理などにAI技術が活用されています。これらのシステムでは、リアルタイムでのデータ処理と制御が重要で、大学で学んだ組込システムや制御工学の知識を直接活かせます。環境負荷の軽減と効率性の両立を図る技術として、社会的意義の高い分野です。
院卒 vs 学部卒、採用の傾向
院卒と学部卒では、それぞれ異なる評価ポイントと採用傾向があります。院卒は研究経験の深さと専門性が評価され、研究開発職での採用が多い傾向にあります。学部卒は幅広い適応性と成長ポテンシャルが重視され、多様な職種での活躍が期待されます。どちらも企業にとって価値のある人材であり、個人の志向と企業のニーズに応じて選択することが重要です。新卒採用では、学歴よりも学習意欲と人物評価が重視される傾向が強まっています。
未経験スキルの補い方
在学中に未経験のスキルを補うためには、計画的な学習と実践が重要です。オンライン学習プラットフォーム、技術書籍、大学の授業外学習などを活用し、段階的にスキルを習得します。特に実際のプロジェクトを模擬した課題や研究室での実験を通じて、実務に近い経験を積むことが効果的です。また、資格取得や技術系サークルへの参加により、専門知識の定着と人的ネットワークの構築を図ることも重要です。
再挑戦中の学生・若手へのアドバイス
就職活動で思うような結果が得られなかった場合でも、諦めずに継続的な努力を続けることが重要です。自分の強みと改善点を客観的に分析し、不足している部分を補強する具体的な計画を立てます。技術スキルの向上だけでなく、コミュニケーション能力や自己表現力の向上にも取り組みます。
07 まとめ
電気電子工学科で学んだ専門知識は、現代社会の様々な分野で求められる貴重な資産です。新卒として適切な業界選択とスキル開発を行うことで、充実したキャリアのスタートを切ることができます。
株式会社三央では、水・土・空気分野のシステムメーカーとして、新卒の電気電子工学科学生が専門知識を活かせる多様な機会を提供しています。環境事業と土木事業を通じて社会インフラを支え、技術者として大きな達成感と成長を実感できる職場環境が整っています。新卒者向けの充実した研修制度により、未経験からでも段階的にスキルアップを図ることができ、「自律型社員」として活躍できるよう全面的にサポートしています。
私たちと一緒に、技術力で社会貢献を実現し、「地球と人が共存できる未来」の創造に挑戦してみませんか。詳しくは採用サイトをご覧ください。








































































































