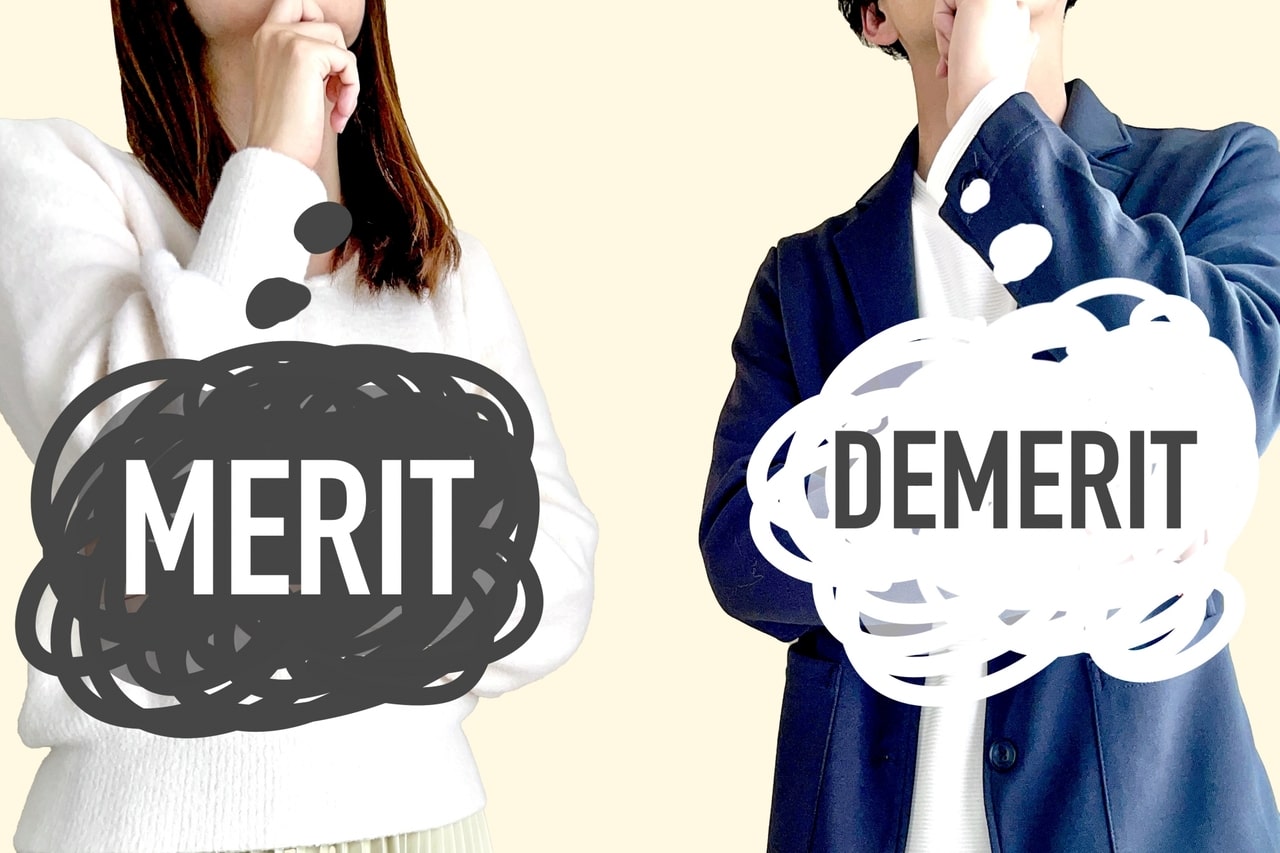01 ESの「ですます調」と「である調」とは?基本的な違いを理解する

ESで文体を選ぶ際は、まず「ですます調」と「である調」の基本的な特徴を理解しておくことが大切です。この理解があれば、自分の伝えたい内容に適した文体を判断しやすくなります。「ですます調」は敬体とも呼ばれ、「です」「ます」で文を締める丁寧な文体です。読み手に敬意を示し、親しみやすく丁寧な印象を与えます。例えば、「私は営業職を志望します」「大学では経済学を専攻しています」といった表現が挙げられます。
一方、「である調」は常体と呼ばれ、「だ」「である」で文章を終える文体です。簡潔で力強い印象があり、学術論文や新聞記事などでよく用いられます。例として、「私は営業職を志望する」「大学では経済学を専攻している」といった表現があります。株式会社三央のような技術系企業では、論理的思考力に加えてコミュニケーション能力も重視されるため、文体選択には慎重な配慮が求められます。
02 ESで好まれる文章調の傾向と企業側の視点
企業の人事担当者は、ESの文体から応募者の人柄やビジネスマナーへの理解度を判断しています。そのため、現在の就職活動ではどちらの文体が好まれる傾向にあるかを把握することが大切です。多くの企業では、応募書類であるESに対して丁寧で礼儀正しい「ですます調」を推奨する傾向があります。一方で、「である調」は学術的で格調高い印象を与える反面、場合によっては距離感を感じさせることもあります。
ただし、業界や企業文化によって好みは異なります。研究開発職や技術職を中心に募集する企業では、論理的で簡潔な「である調」を好むケースも見られます。
株式会社三央のような環境・土木分野のシステムメーカーでは、技術的な提案力とともに顧客との円滑なコミュニケーション能力も重視されるため、丁寧な表現が好まれる傾向にあります。最も重要なのは、企業研究を通じてその企業の文化や求める人物像を理解し、適切な文体を選択することです。迷った場合は、「ですます調」を選ぶのが無難と言えるでしょう。
03 「ですます調」をESで使うメリットと注意点
丁寧さや誠実さを伝える効果
「ですます調」をESで使う最大のメリットは、読み手に対して敬意や誠実さを伝えられる点です。採用担当者に親しみやすい印象を与え、好感度を高める効果が期待できます。この文体は、応募者の人柄の良さやビジネスマナーの理解を示すのに適しています。特に営業職や接客業を志望する場合、顧客対応力の高さをアピールする際にも効果的です。例えば、「私は顧客のニーズを深く理解し、最適なソリューションを提案したいと考えています」といった表現で、親近感と専門性を両立させることができます。
株式会社三央のような環境・土木分野の企業では、多様なステークホルダーとの調整力が求められるため、丁寧なコミュニケーション能力を伝えやすい「ですます調」は有効な選択肢と言えます。
誤用や堅苦しくなるリスク
一方で、「ですます調」を使う際には注意も必要です。過度に丁寧すぎる表現は堅苦しい印象を与え、かえって読みづらくなることがあります。よく見られる誤りとしては、二重敬語や不自然な敬語表現があります。例えば、「拝見させていただきます」や「お聞かせいただければと思います」といった過剰な敬語は逆効果になることも少なくありません。
また、文字数制限のあるESでは、丁寧語を多用しすぎると肝心の内容が薄くなりやすい点にも注意が必要です。「ですます調」を効果的に使うためには、シンプルで自然な表現を心がけることが重要です。
04 「である調」をESで使うメリットとデメリット
力強さや説得力のある印象を与える効果
「である調」の最大の特徴は、簡潔で力強い表現によって説得力のある文章を作成できる点にあります。限られた文字数の中で多くの情報を伝えたい場合に適した文体といえます。この文体は、自信や主体性を示すのに適しており、「私は困難な課題に対して論理的なアプローチで解決策を見出す」「チームリーダーとして全体最適を追求する」といった表現で、リーダーシップや問題解決能力を力強くアピールできます。
研究職や技術職、コンサルティング業界など、論理的思考力や専門性が求められる分野では「である調」が好まれることが多いです。株式会社三央の技術研究開発職のような専門性の高い職種では、技術的な知見を簡潔に伝えるのに「である調」が効果的な場合もあります。
堅すぎて冷たい印象を与える可能性
「である調」のデメリットとしては、読み手との距離感が生まれやすい点が挙げられます。特に人物重視の選考では、親しみやすさが不足していると評価されることがあります。また、「である調」に慣れていない学生が使うと、不自然で読みづらい文章になる場合があります。学術論文のように堅苦しい表現となり、エントリーシート(ES)としての魅力を損なうリスクもあります。
使用する際は、適度な柔らかさを残しつつ、読み手への配慮を忘れない表現を心がけることが大切です。
05
ES文章の語尾や敬語の正しい使い方のポイント
敬語と「ですます調」の基本マナー
ESでの敬語使用においては、基本的なビジネスマナーを理解しておくことが非常に重要です。正しい敬語を使うことで、社会人としての基礎的な素養や礼儀正しさをアピールできます。尊敬語、謙譲語、丁寧語の使い分けを正確に行い、相手に対して適切な敬意を示しましょう。また、「貴社」と「御社」の使い分けや、「いたします」「させていただきます」などの表現の適切な使用法を身につけることも大切です。
「思います」「考えます」などの適切な表現例
ESでよく使われる「思います」「考えます」といった表現には、それぞれ適した使い方があります。これらを使い分けることで、自分の意見や考えをより正確に伝えられます。「思います」は主に感情や印象を表す際に用い、「考えます」は論理的な思考や判断を示す場合に適しています。例えば、「貴社の環境事業に魅力を感じます」は感情を、「持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています」は論理的な意志を伝えています。
また、「目指します」は将来の目標や抱負を述べる際に使います。株式会社三央のような技術系企業では、感情面と論理面のバランスを意識した表現で、人間性と専門性の両方をアピールすることが重要です。
| 表現 | 使用場面 | 例文 |
|---|---|---|
| 思います | 感情・印象 | 「貴社の技術力に魅力を感じます」 |
| 考えます | 論理的思考・判断 | 「環境保全に貢献したいと考えます」 |
| 目指します | 目標・抱負 | 「技術者として成長を目指します」 |
06 ESにおける「ですます調」と「である調」の統一の重要性
調の混在が与える印象とリスク
ES作成で最も重要なのは、文体の一貫性を保つことです。「ですます調」と「である調」が混ざると、読み手に違和感を与え、応募者の注意力や文章力に疑問を持たれる恐れがあります。文体の混在は、細部への配慮不足や集中力の欠如を印象づけるため、特に金融業界や法務関係など正確性が求められる分野では、致命的なマイナス評価につながることもあります。
一貫性を保つための具体的な工夫
文体の一貫性を保つためには、ES作成前に使用する文体を決め、最後までその文体を貫くことが重要です。下書きの段階で文体を統一し、完成後は全体を通して文体の乱れがないかを必ず確認しましょう。具体的には、各段落の冒頭と末尾の文をチェックし、異なる文体が混在していないかを確かめます。また、第三者に読んでもらい、客観的な視点から文体の統一性についてフィードバックをもらうことも効果的です。
株式会社三央のような技術系企業では、正確さと一貫性が重視されるため、こうした細かな配慮が高く評価されます。
07 自己PRでの「ですます調」と敬語の使い方例
丁寧かつ好印象な自己PR文章サンプル
効果的な自己PRでは、「ですます調」を用いて親しみやすさと専門性のバランスをとることが大切です。具体的なエピソードを交えながら、自分の強みをわかりやすく伝えましょう。
例えば、
「大学では環境工学を専攻し、水質浄化技術の研究に取り組んでいます。特に産業排水の処理効率を向上させるプロジェクトでは、従来の手法と比べて20%の効率改善を達成しました。この経験から、技術的な課題に対して論理的にアプローチする力と、チームで協力して問題を解決する重要性を学びました。貴社の環境事業において、これらの技術的知見と協調性を活かして貢献したいと考えています。」
よくある誤用例と改善方法
自己PRでよく見られる誤りの一つに、過度な謙遜表現や不自然な敬語の使用があります。例えば、「つたない経験ですが」「未熟者ですが」といった自己を過度に下げる表現は、かえって自信のなさを印象づけてしまいます。改善するには、事実を客観的に伝え、その成果や学びを明確に示すことが大切です。謙遜よりも具体的な成果や学習内容を示すことで、より説得力のある自己PRになります。
08 実際のES文例:適切な「ですます調」での書き方サンプル
実際のES作成では、具体的な文例を参考にすることが効果的です。以下は技術系企業への応募を想定した「ですます調」の例文です。
「私は環境問題の解決に技術で貢献したいと考え、貴社を志望いたします。大学では水質浄化技術の研究に取り組み、実験データの分析を通じて課題解決のプロセスを学びました。また、研究室のチームプロジェクトではメンバー間の意見調整を行い、目標達成に向けて協力することの重要性を実感しました。貴社の環境事業において、技術的な専門知識と協調性を活かし、持続可能な社会の実現に貢献したいと思います。」
この例文は、志望動機から具体的な経験、そして将来の抱負まで「ですます調」で統一されており、読みやすく親しみやすい文章となっています。
09 ES作成時に避けたいNG表現と語尾の注意点

ES作成で避けるべき表現として、曖昧な表現や消極的な語尾があります。たとえば、「~と思われます」「~かもしれません」といった不確実な表現は、自信のなさを感じさせてしまいます。また、「~していただく」の多用も注意が必要です。適度な謙遜は必要ですが、過度にへりくだりすぎると主体性の欠如と見なされる可能性があります。
具体的で明確な表現を心がけ、自分の考えや経験を確信を持って伝えることが大切です。株式会社三央のような技術系企業では、明確な意思表示と論理的な思考が重視されるため、曖昧な表現は特に避けるべきでしょう。
10 まとめ:ESは「ですます調」か「である調」どちらが最適か?
ESの文体選択において、多くの場合「ですます調」が最適です。丁寧さと親しみやすさを兼ね備え、多くの企業で好印象を与えやすいためです。しかし、応募先の業界や企業文化、募集職種によって適切な文体は異なります。たとえば、研究職や技術職など専門性が求められる分野では「である調」が効果的な場合もあります。大切なのは、企業研究をしっかり行い、適切な文体を選択したうえで最後まで一貫して使うことです。
迷った場合は「ですます調」を選び、正確な敬語の使用と具体的な内容で差別化を図ることをおすすめします。
最終的に評価されるESを作成するには、文体選択以外にも重要なポイントがあります。具体性、論理性、そして独自性を意識した文章作成が求められます。具体的なエピソードを交えて、自身の経験や学びを表現し、その企業でなければならない理由を明確に示すことが大切です。また、誤字脱字のチェックや適切な文字数で作成するなど、基本的な確認も忘れないようにしましょう。
株式会社三央では、「自律型社員」として能動的に考え、常に問題意識を持ち改善に取り組む人材を求めています。環境事業や土木事業における技術革新への挑戦に共感し、自身の成長と社会貢献を両立させたいという強い意志を持つ方にとって理想的な職場環境です。
東証プライム上場グループの安定した基盤のもと、ニッチトップ企業として独自の立ち位置を活かし、新しいことに挑戦しながら着実にキャリアを積むことができます。ぜひ、あなたの可能性を最大限に発揮してみませんか。