01 電験1種とは?試験の概要と特徴

電験1種は、電気設備に対する制限がない最上位の国家資格であり、大規模な発電所や変電所の保安監督を担当できる資格として位置づけられています。その権威と希少性から、電気業界で高く評価されています。正式名称は「第一種電気主任技術者」といい、電気事業法に基づいた国家資格です。すべての電気設備の工事、維持、運用に関わる保安監督業務を行うことが可能であり、電圧や出力の制限がないため、原子力発電所や大型火力発電所などの重要なインフラ設備も担当できます。
試験は年に一度行われ、一次試験(筆記)は理論・電力・機械・法規の4科目、二次試験(記述式)は電力・管理と機械・制御の2科目から成ります。科目ごとの合格制度が採用されているため、段階的に合格を目指すことも可能です。
環境・土木分野のインフラ整備に取り組む株式会社三央では、電気設備に関する専門知識を持つ技術者が重要な役割を果たしており、こうした資格保有者に対する期待が高まっています。
02 電験1種の難易度を具体的に解説
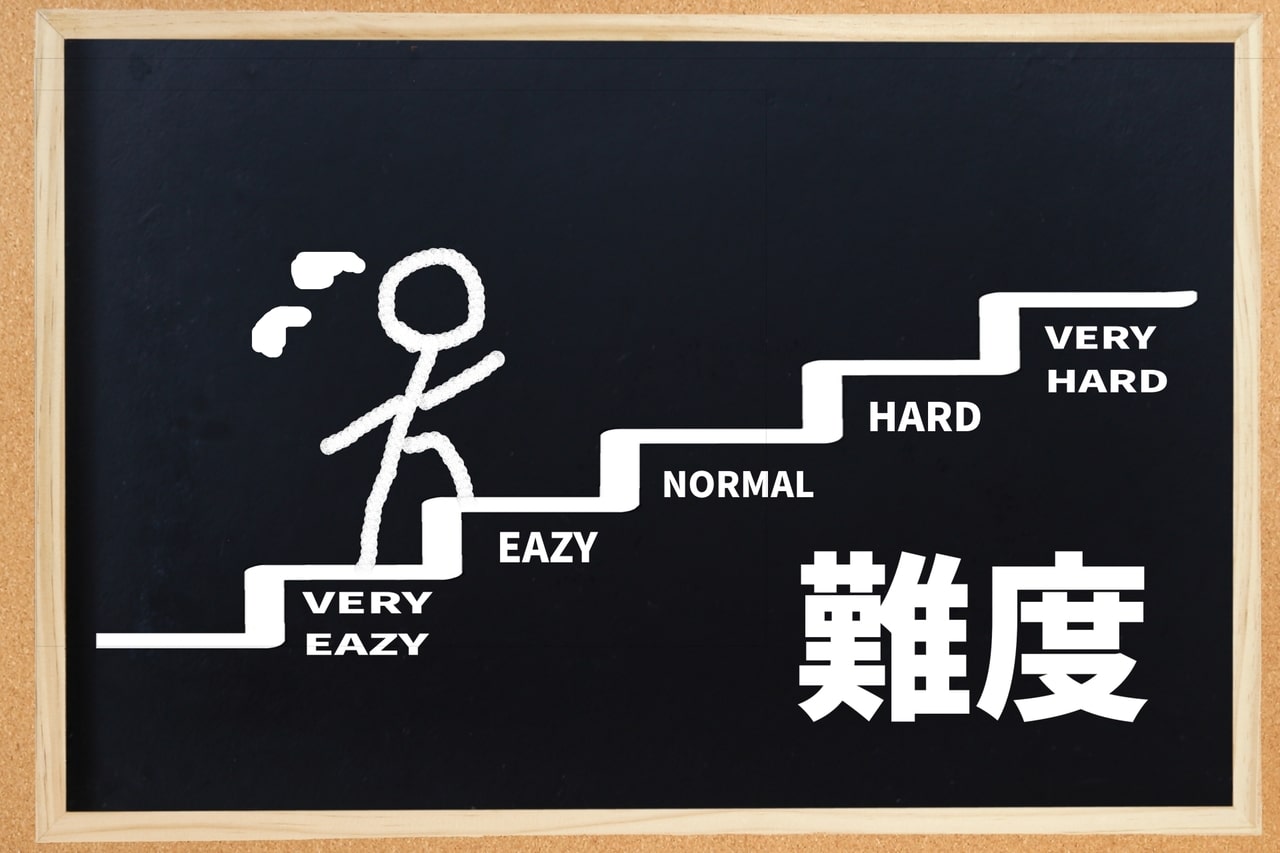
電験1種は難易度が高い国家資格の一つで、一次試験の合格率はおおむね15~20%程度とされています。最終的な合格率は約3~5%と低く、電気技術者にとっては非常に挑戦しがいのある資格です。
合格率から見る難易度の実態
電験1種の合格率は例年低く、一次試験の通過率はおおよそ15~20%、二次試験の合格率は約20~30%と報告されています。これらを踏まえた最終合格率はおおむね3~5%程度にとどまります。受験者の多くは電験2種合格者や実務経験を持つ技術者であるため、この数字の難しさがうかがえます。年間の合格者数は100~200名程度と少なく、電気工学の博士号を持つ方でも簡単には合格できない難関資格です。大手電力会社の経験豊富な技術者であっても、複数回受験して合格を目指すことが珍しくありません。
試験科目ごとの難しさのポイント
一次試験では、理論科目の過渡現象や電磁気学、電力科目の系統解析、機械科目のパワーエレクトロニクス、法規科目の電気事業法施行規則などが難しいポイントとされています。これらの科目では、大学院レベルの数学的解析能力が求められることもあります。二次試験は記述式で、計算の過程を論理的に説明する力や、実務に即した判断力が問われます。電力・管理の科目では系統保護や運用計画、機械・制御の科目では制御理論や電動機の詳細設計などが出題され、単純な暗記だけでは対応が難しく、応用力が必要とされます。
電験1種の壁となる分野とは
電験1種の中でも特に難関とされるのが、電力系統の保護協調や制御理論の応用分野です。これらの分野では、理論的な知識に加え、実務経験も伴った深い理解が求められます。具体的には、故障時の計算に用いる対称座標法の理解、保護継電器の動作原理と整定計算、そして現代制御理論を活用した電力系統の安定化制御などが挙げられます。これらの内容は、発電所や変電所での実務経験がなければ習得が難しいケースが多く、受験者がつまずきやすいポイントとなっています。
03 電験1種と電験2種・3種の違い
電験資格は第三種から第一種までの3段階に分かれており、それぞれ難易度や担当できる電気設備の規模が異なります。これらはそれぞれ異なる役割を持つ、電気業界で重要視される国家資格です。
電験3種の難易度と役割
電験3種は、電圧5万ボルト未満の電気設備の保安監督が可能な資格で、電験の入門資格として位置づけられています。合格率は例年約8~12%と、難易度は適度なレベルです。主に工場やビルの受電設備、太陽光発電所などの保安監督業務が担当範囲となります。
勉強時間の目安は800~1,200時間程度とされており、電気の基礎知識を持つ方であれば1~2年で取得可能な場合もあります。試験は理論・電力・機械・法規の4科目で構成され、基本的な電気回路や電気機器の動作原理の理解が求められます。
電験2種の特徴と1種との難易度比較
電験2種は、電圧17万ボルト未満の電気設備を担当できる国家資格で、一次試験の合格率は約25%、二次試験は約15%、最終合格率は4~6%程度となっています。電験1種との大きな違いは、取り扱える電圧の上限にあり、超高圧送電線や大型変電所の管理は1種の担当範囲です。
| 項目 | 電験1種 | 電験2種 |
|---|---|---|
| 取扱電圧 | 制限なし | 17万ボルト未満 |
| 合格率 | 3~5% | 4~6% |
| 勉強時間 | 2,000~3,000時間 | 1,500~2,000時間 |
| 二次試験 | 記述式2科目 | 記述式2科目 |
電気工事士三種や他資格との違い
電気工事士は主に電気設備の工事を担当する資格であるのに対し、電験は電気設備の保安監督を行う資格という点で大きく異なります。電気工事士1種の工事範囲は最大電圧60万ボルト以下に限られていますが、電験1種のように電圧制限がないわけではありません。
その他の電気関連資格としては、技術士(電気電子部門)や電気通信主任技術者などがありますが、これらは特定の専門分野に特化しており、電験1種ほど幅広く包括的な電気設備の管理権限を持つわけではありません。
04 電験1種合格に必要な勉強時間と効率的な学習法

電験1種の合格には、十分な準備期間と計画的な学習が欠かせません。効率的な学習方法を取り入れることで、合格の可能性をより高めることが可能です。
推奨される勉強時間の目安
電験1種の合格に必要な勉強時間は約2,000~3,000時間が目安とされており、電験2種保有者でも最低でも約1,500時間の追加学習が必要とされており、1日3時間の学習を続けた場合、合格までにおよそ2〜3年かかる計算になります。電気系の学科出身者でも約2,000時間、非電気系出身者は3,000時間以上の学習時間を見込んでおくのが安全です。
例えば、大手メーカーの技術者の中には、平日は2時間、休日は5時間の学習を2年間継続して合格を達成したケースも多く報告されています。
効果的な勉強計画の立て方
段階的な学習法が最も効果的で、まず一次試験の基礎固めから始め、徐々に応用問題へとステップアップすることが重要です。
学習計画の一例としては、1年目に基礎理論をしっかり理解し、2年目前半で応用問題の演習を行い、2年目後半で二次試験対策と過去問演習に取り組む流れが推奨されます。
特に大切なのは、すべての科目を同時に並行学習するのではなく、理論→電力→機械→法規の順序で段階的に学習内容を積み上げていくことです。
参考書や講座の活用方法
基本書は各科目1冊に絞り込み、それを完璧に理解することが合格への近道です。過去問題集は最低10年分を3回以上繰り返し、出題傾向を完全に把握することが必要です。
通信講座や予備校の活用も有効で、特に二次試験の記述対策では専門講師からの添削指導が重要な役割を果たします。独学が困難な制御理論や系統解析などの分野では、専門講座の受講を検討することをおすすめします。
05 電験1種合格のポイントと成功の秘訣
電験1種合格には、継続的な学習習慣の確立と、苦手分野を徹底的に克服することが重要です。特に、日々の学習時間を確保する仕組みを作り、理解が不十分な分野から逃げずに向き合う姿勢が合格への鍵となります。
効果的な学習法としては、過去問を解く際に解答をすぐに確認せず、自力で解けるまで繰り返すことや、間違えた問題を翌日に再度取り組む復習体制を整えることが挙げられます。
また、実務経験がある場合は、実際に扱う設備に関連した問題から学習を始めることで、理論と実践の結びつきを理解しやすくなります。
株式会社三央のような技術革新に積極的に取り組む企業では、資格取得支援体制を整備しており、技術者のスキルアップやキャリア形成を支援しています。
06 電験1種の合格後に期待できるキャリアメリット

電験1種の取得により、専門性の高い業務に従事できるようになり、電気業界での評価が高まります。これに伴い、昇進や給与面での改善が期待でき、キャリアの選択肢も広がることが多いです。特に大規模設備の管理や保安監督業務を任されることで、技術者としての市場価値向上につながります。
電気主任技術者1種の資格価値と年収相場
電験1種保有者の年収相場はおおむね800万円から1,500万円と高水準で、特に電力会社や大手重電メーカーでは管理職ポストへの登用や資格手当の支給が一般的です。資格手当は月額3万円から10万円程度が多く、年間に換算すると36万円から120万円の収入増加につながります。
また、大手電力会社では、電験1種取得者に対して基本給の10〜15%相当の特別手当を支給するケースもあります。さらに、独立してコンサルタント業務を行う場合は、月額50万円以上の収入を得ることも期待されます。
ただし、これらの数値は目安であり、勤務先や役職、経験年数によって変動する点に注意が必要です。
企業での役割や昇進への影響
電験1種保有者は技術部門の管理職候補として評価されることが多く、課長や部長クラスへの昇進において有利な立場に立てます。特に電力インフラや重要産業設備を扱う企業では、管理職の必須条件として電験資格を求めるケースも増加しています。
また、転職市場においても高い専門性が認められ、ヘッドハンティングの対象となることが少なくありません。環境・インフラ分野で技術力を発揮する株式会社三央のような企業では、電験資格保有者の専門知識を活かし、新規事業の開発や技術提案など重要な役割を担うことが期待されています。
07 電験1種に挑戦する前に知っておくべきポイントと心構え
電験1種は最難関の国家資格であり、長期間の計画的な学習が不可欠です。成功の鍵は、明確な目標設定と継続的な学習習慣の確立にあります。合格への道のりは決して簡単ではありませんが、適切な準備と心構えがあれば十分に達成可能です。
まずは現在の知識レベルを正確に把握することが重要です。電験2種を未取得の場合は、まずは段階を踏んで2種合格を目指すことを推奨します。また、実務経験の有無によって学習方法や取り組み方が異なるため、自身の立ち位置を明確に理解しておくことが大切です。学習環境の整備も継続のために欠かせません。静かな学習スペースの確保や参考書・問題集の準備、さらには家族の理解と協力も長期学習を支える大きな力となります。場合によっては「3年間は趣味や娯楽を控える」といった覚悟も必要かもしれません。
また、失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢も重要です。多くの合格者は複数回の受験を経て合格しており、一度の不合格であきらめる必要はありません。受験のたびに自分の学習到達度を確認し、着実にレベルアップを図ることが合格への近道です。
株式会社三央では、「水・土・空気」の環境分野における高度な技術力と、東証プライム上場グループの安定した経営基盤を背景に、技術者一人ひとりの成長を全力で支援しています。
専門性の高い資格取得を目指す技術者にとって、当社の充実した教育制度と多様な成長機会は理想的な環境です。技術で社会のインフラを支え、地球と人が共存できる未来を創造するという、やりがいある仕事に挑戦してみませんか。








































































































