01 離職率とは?就活・転職で知っておくべき基礎知識

離職率は企業の働きやすさを判断する重要な指標の一つです。正しい理解と計算方法を知ることで、企業選びの精度を高めることができるでしょう。
離職率の定義と算出方法
離職率とは、一定期間内に退職した従業員の割合を示す数値です。一般的に「年間離職率」として計算され、次の式で算出されます。
離職率(%)= 年間退職者数 ÷ 期首従業員数 × 100
たとえば、期首に100人の従業員がいて、1年間で10人が退職した場合、離職率は10%となります。この数値が低いほど、従業員が定着しやすい職場環境であると考えられます。
「3年以内離職率」「勤続年数」の意味
3年以内離職率は、新卒入社者が3年以内に退職する割合を示します。厚生労働省の調査によると、大学卒業者の3年以内離職率は約30%となっています。
勤続年数は従業員が同じ会社で働き続けている期間を表し、平均勤続年数が長い企業ほど安定した職場環境を提供している可能性があります。これらの指標を組み合わせて判断することで、より正確な企業評価が可能になるでしょう。
02 離職率が低い会社の基準と目安
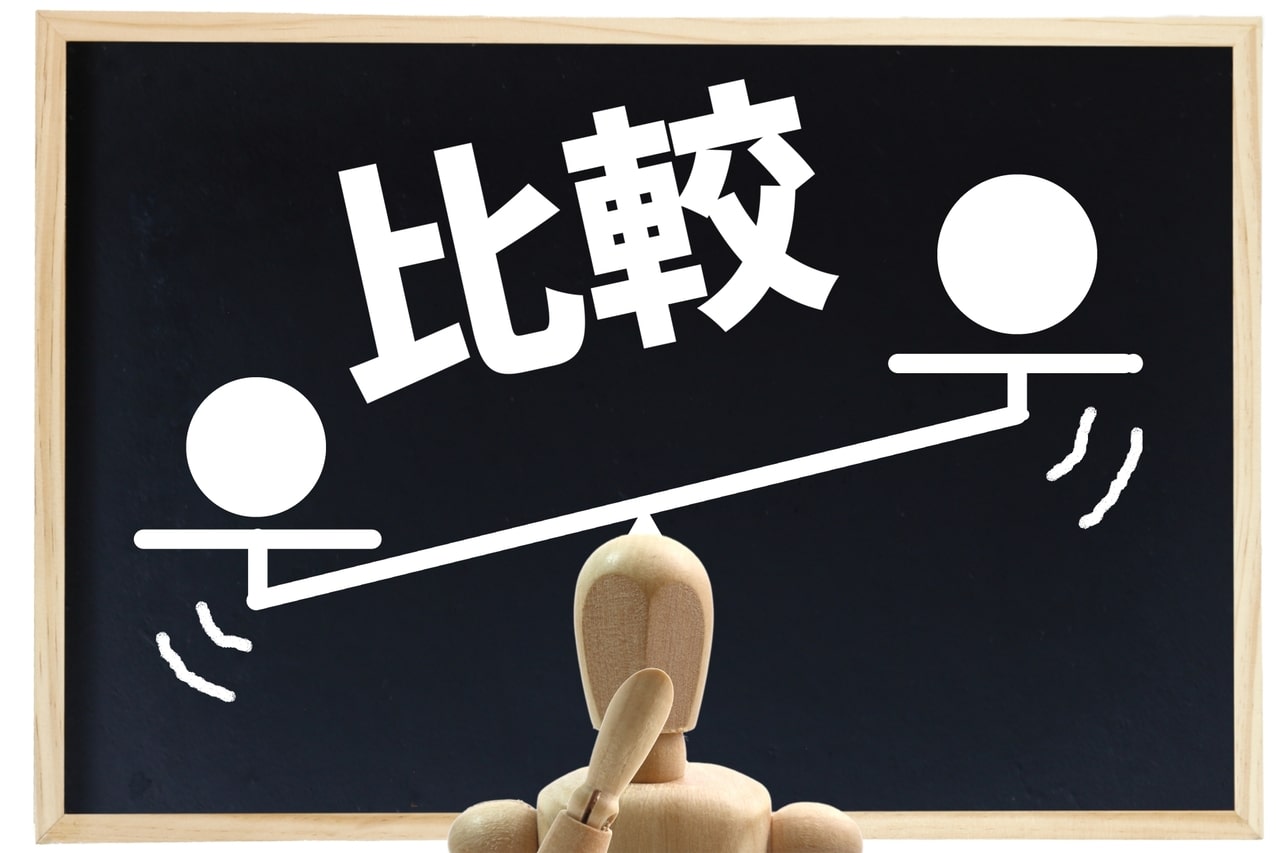
離職率の数値を正しく評価するためには、業界平均や一般的な基準を知っておくことが重要です。ここでは具体的な数値基準について解説します。
日本全体の平均離職率と比較
日本全体の年間離職率は約14~15%となっています。この数値を基準として、企業の離職率を評価することが一般的です。
業界によって離職率には大きな差があり、製造業では比較的低い傾向にある一方で、宿泊業や飲食サービス業では高い数値を示しています。株式会社三央のような土木・環境関連のシステムメーカーでは、専門性の高い技術を要するため、従業員の定着率が高くなる傾向があります。
何%以下なら「低い」と言えるのか
一般的に、年間離職率が以下の水準であれば「低い」と判断できます。
- 10%以下:非常に低い(優秀な水準)
- 10~15%:平均的~やや低い水準
- 15%以上:平均以上~高い水準
ただし、業界特性を考慮した判断が必要です。たとえば、技術系企業では専門スキルの習得に時間がかかるため、離職率が自然と低くなる傾向があります。
勤続年数から見る安定性の指標
平均勤続年数の目安は次の通りです。
・15年以上:非常に安定した職場環境
・10~15年:比較的安定
・10年未満:業界平均程度
長期的な雇用安定性を重視する方は、平均勤続年数15年以上の企業を目安にすると良いでしょう。
03 離職率が低い会社の特徴

離職率が低い会社には共通する特徴があります。これらの要素を理解することで、働きやすい職場環境を見極めることが可能になります。
教育制度・研修が整っている
離職率が低い会社では、従業員の成長をサポートする教育制度が充実しています。
具体的には、新人研修から管理職研修まで段階的な教育プログラムが用意されており、従業員が安心してスキルアップできる環境が整備されています。
株式会社三央では「会社も社員も一緒に成長していきたい」という想いから、入社後の確実なスキルアップが叶うよう教育に力を入れており、入社段階での知識やスキルがなくても安心して働けます。
研修制度の充実は従業員のモチベーション維持にも大きく貢献し、結果として離職率の低下につながるのです。
ワークライフバランスを重視している
働きやすい職場環境の構築により、従業員の満足度向上を図っている企業では離職率が低くなります。
・柔軟な働き方制度(リモートワーク、フレックスタイム等
・有給休暇の取得推進
これらの取り組みにより、従業員が仕事とプライベートのバランスを保ちながら働けるため、長期勤続が促進されます。特別休暇制度や充実した福利厚生を提供する企業では、従業員の定着率が高い傾向にあります。
職場に心理的安全性や風通しの良さがある
従業員が安心して意見を言える職場環境は、離職率の低下に大きく影響します。
上司や同僚とのコミュニケーションが活発で、問題や課題について気軽に相談できる雰囲気があることが重要です。また、失敗を恐れずにチャレンジできる文化があることで、従業員のやりがいや成長実感が高まり、長期勤続につながります。
心理的安全性の高い職場では、従業員のストレスが軽減され、職場への満足度が向上する可能性があります。
公平な評価制度とキャリア支援がある
透明性の高い評価制度は、従業員のモチベーション維持に欠かせない要素です。
年齢や勤続年数に関わらず実力をしっかり評価する環境があることで、従業員は公平感を持って働くことができます。
株式会社三央では能力等級制度により、高い目標に対して成果を上げた社員を正当に評価し、「頑張った人」や「成果を残した人」が評価される仕組みを構築しています。
また、キャリアパスが明確に示されており、将来的な成長見通しを持てることも重要な要素となります。
04 離職率が低い業界・高い業界の違い

業界によって離職率には大きな差があります。業界特性を理解することで、自分に適した職場環境を選択しやすくなるでしょう。
離職率が低い代表的な業界
以下の業界は一般的に離職率が低いとされています。
- 製造業:技術の専門性が高く、安定した雇用環境
- インフラ・公共事業関連:社会的使命感と安定性
- 金融業:安定した経営基盤と充実した福利厚生
特に、株式会社三央のような土木・環境事業を手がけるシステムメーカーでは、「水・土・空気」分野の専門技術を持つ人材が重要視され、長期的な技術継承の観点からも従業員の定着が図られています。
国として取り組むビッグプロジェクトに貢献できるやりがいも、離職率の低さに寄与しています。
離職率が高いと言われる業界の特徴
一方で、以下の業界では離職率が高い傾向にあります。
- 宿泊業・飲食サービス業:労働条件の厳しさや不規則な勤務形態
- 小売業:接客ストレスや長時間労働
これらの業界では、労働環境の改善や働き方改革の取り組みが重要な課題となっています。ただし、同じ業界内でも企業によって大きな差があるため、個別の企業評価が必要です。
業界選びの際に注意すべきポイント
業界選択では以下の点に注意しましょう。
業界平均の離職率だけでなく、その企業独自の取り組みや風土を詳しく調査することが重要です。たとえば、一般的に離職率が高いとされる業界でも、従業員の働きやすさを追求する企業では低い離職率を実現している場合があります。
05 離職率が低い会社で働くメリットとデメリット

離職率が低い会社での勤務には、メリットとデメリットの両面があります。自分のキャリア目標と照らし合わせて判断することが大切です。
安定して長く働けるメリット
離職率が低い会社で働く主なメリットをご紹介します。
- 安定した雇用環境:長期的なキャリア形成が可能
- 充実した福利厚生:退職金制度や各種手当の恩恵
株式会社三央では、借り上げ社宅制度や業績賞与、長期所得補償保険など充実した制度により、社員が長く働けるような環境を整備しています。また、東証プライム上場のニシオホールディングス株式会社のグループ企業として、大手の安定感を活かしながら新しいことに挑戦できる環境が整っています。
成長スピードが遅くなる可能性などデメリット
一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。
- 変化のスピードが遅い:新しい取り組みや制度変更に時間がかかる場合
- 昇進競争の激化:長期勤続者が多いため、ポジション獲得が困難になる可能性
ただし、これらのデメリットは企業によって大きく異なります。技術革新を積極的に取り入れている企業では、安定性と成長性を両立している場合も多く見られます。
自分に合った環境かを見極める重要性
離職率の低さだけでなく、自分のキャリア目標や価値観と合致するかを総合的に判断しましょう。
安定性を重視するのか、成長スピードを重視するのか、自分の優先順位を明確にすることが重要です。また、業界の将来性や企業の成長戦略も含めて検討することで、より適切な判断ができるでしょう。
06 離職率が低い会社を見分ける方法

実際に離職率が低い会社を見分けるためには、複数の情報源を活用した多角的な調査が必要です。効果的な調査方法をご紹介します。
求人票や会社説明で確認すべき項目
求人票や企業の公式情報で以下の項目を確認しましょう。
- 平均勤続年数:具体的な数値が公開されているか
- 福利厚生の内容:退職金制度、各種手当の充実度
- 教育制度:研修プログラムの詳細
株式会社三央のような企業では、採用サイトで具体的な制度や社風について詳しく説明しており、透明性の高い情報開示を行っています。こうした姿勢は、企業の信頼性を判断する重要な材料となります。
面接やOB訪問で聞いておくべき質問例
直接的な質問を通じて、より詳細な情報を収集しましょう。
具体的な質問例をご紹介します。
- 「実際の離職率はどの程度ですか?」
- 「長く働いている社員の方の特徴を教えてください」
- 「キャリアアップの具体的な道筋について聞かせてください」
これらの質問により、数値だけでは分からない職場の実態を把握することが可能になります。
口コミサイトや公的データの活用法
第三者機関の情報も有効活用しましょう。
厚生労働省の「若者雇用促進総合サイト」では、企業の離職率や有給取得率などの公的データを確認できます。また、転職口コミサイトでは実際に働いた経験のある社員の生の声を参考にすることができます。
ただし、口コミ情報については個人の主観が含まれるため、複数の情報源と照らし合わせて総合的に判断することが重要です。
| 情報源 | メリット | 注意点 |
| 公的データ | 客観的で信頼性が高い | 最新情報でない場合がある |
| 企業公式情報 | 詳細な制度情報 | 良い面が強調される傾向 |
| 口コミサイト | 実体験に基づく情報 | 個人の主観が含まれる |
07 まとめ:離職率が低い会社の特徴を理解してキャリア選択に活かそう
離職率が低い会社は、教育制度の充実、ワークライフバランスの重視、公平な評価制度など、従業員が長期的に働きやすい環境を整備しています。ただし、離職率の低さだけでなく、業界特性や個人のキャリア目標との適合性も総合的に判断することが重要です。
求人票の確認から面接での質問、公的データの活用まで、複数の方法を組み合わせて企業研究を行いましょう。
株式会社三央のように、「会社も社員も一緒に成長していきたい」という理念のもと、充実した教育制度と安定した職場環境を提供する企業では、長期的なキャリア形成が期待できます。
東証プライム上場グループの安定基盤を持ちながら、環境事業と土木事業で社会貢献できるやりがいのある仕事に挑戦してみませんか。詳しくは株式会社三央の採用サイトをご覧ください。







































































































